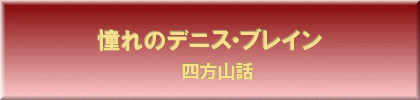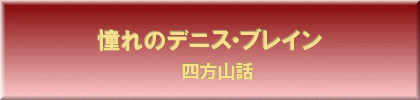| 第168話「フィルハーモニア管弦楽団ブッキングシート」 |
マーシャル教授の「Dennis Brain on Record」とスティーヴン・ペティットのブレイン伝の中のモーツァルトの29番の録音に関する挿話との不一致についてご両人に問い合わせをしました。するとペティットさんが大変ご親切にもフィルハーモニア管弦楽団ブッキングシートの当該部分を教えてくれました。これを見たマーシャル教授、ヒンデミットの《高貴なる幻影》を彼のブレイン・ディスコグラフィーに付け加えるべきとの考えになりました。1954/10/5&6 モーツァルト/41番 ブレインとサンダースがホルンとして出演契約
1954/10/7(午前) ホルン協奏曲のセッションは取り止め
1954/10/7(午後),8&9 《高貴なる幻影》 ブレイン/1番ホルンただし7日以外。
「ウォルター・レッグ曰くブレインは午後のセッションに来るよう説得された」との注釈あり
1954/10/8&9 モーツァルト/29番 チャップマンとサンダース
|
2012年01月08日 10時35分24秒
| |