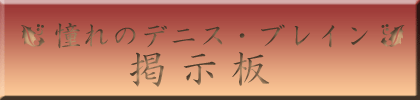
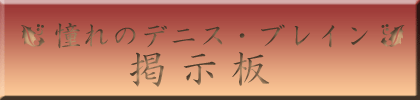
340.ああそれにつけてもブランデンブルグ協奏曲第1番、1956年録音 | |
| name: | 夢中人 - 2003年01月15日 23時40分02秒 |
Favartさんのご好意で聴かせて頂いたデニス・ブレインのバッハ/ブランデンブルグ協奏曲第1番、1956年録音。ボイド・ニール管弦楽団2度目の全曲録音で、カタログ番号 UNLP1040 が第1、2、4番。UNLP1041 が第5、3、6番。ボイド・ニールが残した最後の Decca 録音のひとつであります。 フィルハーモニア管弦楽団のディスコグラフィーを見ると、デニス・ブレインのブランデンブルグ協奏曲のレコーディングがあった7月26日は、前日はオットー・クレンペラーとモーツァルト/交響曲第25番、翌日はフィストラーリとグリーグやボロディンの小品と相変わらず忙しい日々でした。 LPジャケットにデニス・ブレインの名前が出ていないのは EMI との契約の関係上でしょうが、それにしてもこのレコードに関していくつか腑に落ちない点があります。 まず1956年という年からして Decca はどうしてステレオで録音しなかったのか。既にDeccaはEMIに先んじて1954年、アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団とステレオ録音を開始していた筈。EMI は1955年2月にはステレオ録音の実験を開始後もしばらくモノラル録音、ないしモノラルとステレオ両方録音していましたが・・・。 次にFavartさんご指摘の、マスタリングを行ったピーター・バルトーク(あのバルトーク?)の行ったあからさまなテープ編集の跡。第4楽章メヌエットの中のポロネーズの入りはとても唐突で不自然。もう少し間を置いた方が良かった(実は夢中人もこの箇所にはかなり気を使いました)。 ボイド・ニール自身、このようなLPレコードによるテープ編集にはかなり懐疑的で(ブレイン四方山話、第12話「証言・ブランデンブルグ協奏曲第1番」参照)ごまかしのきかないSPモノラル録音を好んだようです。 そのボイド・ニールの伝記で2番ホルンをニール・サンダースではなくノーマン・デル・マーとしていること。ノーマンは1947年にはとっくにホルン奏者から足を洗って、指揮者への道を進んでいました。またそのノーマンが吹いた第1回録音(1945年)をなぜか20年前と記述しているのもおかしい。 そのほか発売当初から Decca レーベルではなく UNICORN RECORDS レーベルであること、その後も Concert Hall や Realistic、Olympic といったマイナー・レーベルでのみ再発されたこと。 以上、イギリスで一世を風靡したアーチストのわりには、この名曲にしていろいろと齟齬の多いレコードにかなりの人が歯痒い思いをしてきたのではないでしょうか。 | |
339.自然ホルンのブラームス | |
| name: | 円号 - 2003年01月13日 16時40分43秒 |
アメリカのグリア―というホルン奏者のものがCDで出ています。彼はモーツアルトの4曲のコンチェルトも自然ホルンで演奏しています。モーツアルトのCD(アメリカ版)はこの頃大手のレコード店でよく見かけます。
| |
338.ラウーとアレキサンダーをもうひとつ | |
| name: | 夢中人 - 2003年01月13日 16時11分27秒 |
ラウーとアレキサンダーによる演奏で、さらに象徴的なものにブレイン父子によるブラームス/ホルン三重奏曲、作品40があるのを忘れていました。 父オーブリー・ブレインとアドルフ・ブッシュ、ルドルフ・ゼルキンによる演奏は、1937年10月10日録音。Testamentの記念すべき第1作(SBT1001、P1990)です。解説書に、曲の初演は1865年12月7日、カールスーエにてブラームスのピアノと、作曲者の要望で「野外」の雰囲気を出すようにヴァルヴの無いホルンを Segisser が吹いたとあります。 またオーブリーの吹くラウー・ラバイエ・モデルが1865年製で、偶然作曲年と同じであり面白いとありますが、イギリス・ホルン協会のマーティン・プローズは、楽器表面に1862年ロンドン万国博覧会の銘があることや記載されている製造元のラウーや代理店のホークス社の住所から判断して、1871年から1876年の製造としています。 息子デニス・ブレインとフィルハーモニア管弦楽団の同僚であるマックス・サルプター、シリル・プリーディによる演奏は、1957年2月15日BBC放送録音。待望のオリジナルからの復刻です(BBC BBCL 4048-2、P2000)。楽器はアレキサンダーB♭シングルですが、解説書中央の写真はラウー・ホルンを吹くデニス・ブレインとピアノがデニス・マシューズ、ヴァイオリンはハリー・ブレックかアルテュール・グリュミオーのいずれかです。 ところでこの三重奏曲、自然ホルンを演奏したディスクがないものかとずっと思っていましたところ、先日ようやく巡り会いました。イギリスの自然ホルンの名手、アンドリュー・クラークによるもので、ピアノもブラームスが活躍した頃のウィーン製ベーゼンドルファーを使用したという懲り様です(EMI CDZ 5 72822 2、P2002) 《参考》 ブレイン・ラウー物語 ブラームス/ホルン三重奏曲、変ホ長調作品40 | |
337.「クレンペラーとの対話」 | |
| name: | CATO - 2003年01月13日 9時37分08秒 |
ご回答ありがとうございます。モーツァルト/ホルン五重奏曲を聴き比べてみます。後日レポートします。皆さんのように所持しているCDが多くないので、少し時間がかかります。 先日から、インタヴュー記録である「クレンペラーとの対話」(白水社1999年復刊版)をゆっくり読み始めています。フィルハーモニア時代に的を絞ったような部分はないようですが、ホルンにふれている箇所もあって、面白いです。私が昨年末、ベートーヴェン7番の第3楽章の「トランペットとゆっくりと壮大にぶち上げるところ」と書いたトリオの部分は、昔の巡礼の歌でアヴェマリアであるので、トスカニーニのように速くやるべきじゃないという語りなんかに感激したりしています。それと、クレンペラーがメンデルスゾーンの子孫と食事した日に起こった傑作エピソードも載っていますが、これは皆さんのお楽しみの為、ここでは紹介しません。 | |
336.ラウーとアレキサンダー | |
| name: | CATO - 2003年01月12日 11時16分44秒 |
夢中人さん。(できれば室内楽の)同じ曲で、(できれば)同じ奏者が、ラウーとアレキサンダーで異なる録音を残しているようなCDがあれば、お教えください。 楽器の「改良」というのも、録音と並んで微妙な問題ですね。 演奏しやすいという意味で、いい楽器というのは、確かにあります。それこそ30年近く前、ヤマハの安物普及版でしかも中古のトランペットを大切にしていた私が、セルマーの輝かしいトランペットを吹ける機会がありました。「風がふくだけでも音が鳴る」ような性能に仰天しました。とにかく楽に吹けることと、薬指によるスライドの滑らかな感触が忘れられません。先日のLSOのTV画面でも、薬指スライドがきれいに写っていました。
| |
335.夢中人様、お礼。 | |
| name: | 大山幸彦 - 2003年01月12日 10時40分43秒 |
これからでかけますので、また後から感想書きますがごていねいに教えていただきありがとうございました。テヴェ先生は「結局その奏者の個人的嗜好の連続(が歴史となる」といいましたが、それを再認識しました。 | |
334.古いロンドン・ホルン事情 | |
| name: | 夢中人 - 2003年01月11日 10時38分04秒 |
戦前のロンドンのオーケストラは、例の「代役制度」の下に離合集散を繰り返していましたが、現在の5大交響楽団の最初が、1904年創立のロンドン交響楽団(LSO)。設立メンバーでもあるフリードリッヒ・アドルフ・ボルスドルフ(1854-1923) はドイツ人で、指揮者のハンス・リヒターが1879年に連れてきました。 ブレインの伝記にありますように、ボルスドルフはザクセンに生まれ、その地でホルンを学びました。渡英後は「郷に入っては郷に従え」でフレンチ・スタイルの細ボアでピストン・ヴァルヴ、F管クルーク付きのラウーを吹き、その音色は、明るく、はっきりとしたもので、フランス風のヴィブラートをかけず、ドイツ流の厚くて暗く、焦点の無い音でもなかったといいます。 王立音楽大学(RCM)と王立音楽アカデミー(RAM)の両方の教授で、教え子にはアルフレッド・ブレイン(1885-1966)とオーブリー・ブレイン(1893-1955)がいました。皆ラウーを吹きました。アルフレッドが1922年、渡米してからというものの、オーブリーは、ロイヤル・フィルハーモニー協会、クイーンズ・ホール管弦楽団、新交響楽団、さらには1924年、LSOとロンドンの一流オーケストラは彼のの独壇場と化します。 ボルスドルフが亡くなって、オーブリーはRAMホルン教授を引き継ぎます。イギリスの伝統に基づいたホルン教育者としても成功して、1936年にはRAMホルン科には50名もの学生がいた、といいます。弟子にはジョン・バーデン、ダグラス・ムーア、アイファー・ジェームズ(b.1931)、アラン・シヴィル(1929-1989) 、ニール・サンダース(1923-1992)らがいます。そして息子のデニス・ブレイン。  一方で1927年、ウィルヘルム・フルトヴェングラーとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のロンドン公演は、そのホルン界に少なからぬ波紋を起こしました(第9の録音があった筈で聴いてみたい)。ロンドン交響楽団のアラン・ハイドは1930年、アレキサンダーのダブル・ホルンを使うことを強く主張、逆に1930年に創設されたBBC交響楽団に移ったオーブリーはセクション全員ラウーを徹し、翌年雑誌で「ドイツのホルンこそユーフォニアムのようだ」と反論を公表しました。 一方で1927年、ウィルヘルム・フルトヴェングラーとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のロンドン公演は、そのホルン界に少なからぬ波紋を起こしました(第9の録音があった筈で聴いてみたい)。ロンドン交響楽団のアラン・ハイドは1930年、アレキサンダーのダブル・ホルンを使うことを強く主張、逆に1930年に創設されたBBC交響楽団に移ったオーブリーはセクション全員ラウーを徹し、翌年雑誌で「ドイツのホルンこそユーフォニアムのようだ」と反論を公表しました。時代の流れ。サー・トーマス・ビーチャムも自分のロンドン・フィルハーモニー管弦楽団(LPO)に全員ドイツ式太ボアホルンを使用するよう要求しました。LPOの創立時(1932年)の首席ホルンは、ボルスドルフの息子フランシス・ボルスドルフ(イギリスに帰化後フランシス・ブラッドリーと改名)でしたが、一シーズンでBBC響に移籍しました。 代わりにLPOの首席に座ったのがチャールズ・グレゴリー。1936年録音のメンデルスゾーン「夜想曲」で伝統の音(恐らくラウー)を聴かせたものの、1939年録音のチャイコフスキー第5では今風な音色でソロを吹きました。楽器の変化が明らかです。楽団で金管の同僚だったマルコム・アーノルドが協奏曲(第1番)を書いて1946年12月8日、コヴェントガーデン、ロイヤル・オペラ・ハウスにて、エルネスト・アンセルメの指揮で初演しました。 LSOのトップは1941年にニール・サンダース、その後デニス・ブレインと同じイギリス空軍バンドにいたジョン・バーデンが1955年にバリー・タックウェル(b.1931)が入団するまで吹きました。名前は特定できませんが、1945年録音、ファリャ「三角帽子」の‘粉屋の踊り’冒頭で聴けるホルン・ソロの音色、は明かにアレキサンダーの特色(びーんとベル全体で鳴る感じ)があります。 戦後、大戦の結果とは裏腹に、ドイツ式楽器はフランス式を駆逐します。1948年、BBC交響楽団の首席に入ったダグラス・ムーアは、オーブリーが守ってきた伝統を破りダブル・ホルンを使用、同年、まだ王立砲兵バンドにいたアラン・シヴィルもアレキサンダーB♭シングルを買いました。 デニス・ブレインにも例外はありません。1950年5月22日、ロイヤル・アルバート・ホール、フルトヴェングラーとフィルハーモニア管弦楽団、「四つの最後の歌」世界初演を含む演奏会。1番デニスがアレキサンダーB♭シングル、2番オーブリーがセルマー(ラウーの後継)を吹いたあの演奏会です。ご存知アレキサンダーへのバイアスです。
| |
333.お詫び | |
| name: | 円号 - 2003年01月10日 23時47分31秒 |
Favart様 お名前を間違えて大変失礼をいたしました。 | |
332.ヴェスコーヴォの「水上の音楽」 | |
| name: | Favart - 2003年01月10日 23時20分06秒 |
円号様、大山様 327〜329のヴェスコーヴォの「水上の音楽」の件、 Lucien ThevetのHPでご説明します。 円号様へ 「憧れのDB」TOP頁下方の紫色のボタンから入れます。 なお、私のペンネームはFavart(ファヴァール)です。 | |
331.(欠番) |
