| ブレイン・ラウー物語 |
ジョゼフ・ラウー |
|
リュシアン・ジョセフ・ |
|
マルセル・オーギュスト・ |
|
ジャック・クリストフ・ |
|
フランシス・ミルロー |
|
ショネアー・ミルロー |
|
アンリ・セルマー |
|
| 1685以前 | ラウー工房、王室御用達の狩りのラッパ(トロンペ・ドゥ・シャッス trompe de chasse)を製造。 |
| 1695頃 | ルーブル広場、パリ行政支部近くにて営業。 |
| 1734 | プティ・リオン通りセント・ソヴェーにて営業。 |
| 1759 | ティクトンヌ通りに地名変更。『パリ名鑑』にホルン教師としてジョセフ・ラウーが掲載される。 |
| 1769 | 元のプティ・リオン通りに地名変更。 |
| 1775 | ジョセフの息子、リュシアン・ラウー、メルシエ通りに工房を設立。 |
| 1776 | ジョセフの息子、リュシアン・ジョセフ・ラウー、メルシエ通りの工房を離れ父と合流。 それを機に、プティ・リオン通りからルーブル広場フロワマントー通りに工房を移転。 |
| 1780 | リュシアン・ジョセフ・ラウー、ハンペル・ヴェルナー式インヴェンション・ホルンの改良形ホルンを発売。管の中央部にD、E♭、E、F、Gの替管を挿入でき、独奏用ホルン(コール・ソロ
cor-solo)として知られる。 設計者テュールシュミットをはじめ、ルブラン、パルザ、プント、プッツィなど多数の名手が採用。 |
| 1785 | 『音楽名鑑』(フランス王太子版)に「ラウー兄弟(父子の誤り)」が掲載される。 |
| 1786 | ロンドンのザロモン演奏会でラウーの一対の銀製コール・ソロがテュールシュミットとバルザによって演奏され、評判となる。 |
| 1787 | 4本の真鍮製楽器がトリーアの宮廷から注文される。 |
| 1794 | 工場、セルパン通り8番に移転。同年(または1800年)ジョセフ引退。1808年まで営業。 |
| 1798 | リュシアン・ジョセフ、パリ音楽院からの委嘱でドプラに贈るコール・ソロ(真鍮製銀の上張り)を製作。 コール・ソロの他、替管が管体の一端に挿入される方式のオーケストラ用ホルン(コール・ドルケストル cor d'orchestre)製造。 |
| 1808 | リュシアン・ジョセフの長男フェルディナンド、ヴィットリアで戦死。 |
| 1809 | セルパン通り13番地に移転。 |
| 1813 | リュシアン・ジョセフの息子、マルセル・オーギュスト・ラウー、ナポレオンの近衛兵の軍楽隊に入る。ホルンをドプラのもとで学ぶ。退役後、父の工場に加わる。 |
| 1816 | セルパン通り11番に移転。1846年まで営業。 |
| 1821 | マルセル・オーギュスト、父の事業を引き継ぐ。 |
| 1822 | マルセル・オーギュスト、イタリア座の第2ホルン奏者に任命される。ついで第1ホルン奏者となる。 |
| 1830 | ラウー、陸海軍省、王立劇場納品業者名簿に記載される。 |
| 1839 | マルセル・オーギュスト、コール・ドルケストルによってパリ博覧会にて金管楽器メーカー銀賞を得る。 シャルル・グノー、マルセル・オーギュストにホルンとピアノのための「6つの旋律」を献呈。 |
| 1844 | マルセル・オーギュスト、博覧会にて金賞を得る。 |
| 1845 | 楽器製造業5社、陸軍省と契約調印したアドルフ・サックスと法廷闘争のため委員会を組織。 |
| 1849 | マルセル・オーギュスト、博覧会金賞と金管楽器製作者として初のレジオン・ドヌールのシュバリエ賞を授与される。 |
| 1850 | セルパン通り14番に移転。1858年まで営業。 |
| 1854 | サックス、保有特許違反金管楽器メーカー申し立て。 |
| 1856 | マルセル・オーギュスト、イタリア座を引退。 |
| 1857 | マルセル・オーギュスト、アドルフ・サックスとの壊滅的法廷闘争に敗れ、事業を年金2400フランにてJ.C.ラバイエに売却。 |
| 1860 | セルパン通り9番に移転。1870年まで営業。 |
| 1875 | ラウー、ラバイエが継承。ミニモ通り14番、14番bに移転。1878年まで営業。 |
| 1885 | ラウー・ラバイエ、ミルローが事業継承。アングレーム通り66番に移転。1895年まで営業。 |
| 1898 | ミルローの養子ショネアーが事業継承。 |
| 1931 | アンリ・セルマーが買収し、1933年までラウー・ブランドで製作。 |
参考:THE NEW LANGWILL INDEX(WILLIAM
WATERHOUSE) |
![]()
イギリスのホルン奏者が愛用したラウーのピストン・ヴァルヴ式ホルンは、パリの老舗管楽器工房、ラウー家3代とその後継者たちによって18世紀の終わりから19世紀頃にかけて生産された。 1857年、マルセル・オーギュスト・ラウーは同じ管楽器のメーカーとしてライバルのアドルフ・サックス社との長い間の競争に敗れ、ラウー工房をジャック・クリストフ・ラバイエ(父は名匠コルトワの弟子)に売却。 ラバイエはラウーと同じ所在地、セルパン通りとミニモ通りで引き続きラウー・モデルを盛んに製作した。オーブリー・ブレイン(1893-1955)の使用したラウー・ラバイエ・ホルンには花文字で次のように刻印されている。
| ラウー 音楽院御用達 ミニモ通り 14、パリ |
ベルのフレアー(広がったところ)には
| J.C.ラバイエ パリ国立劇場向け仕様 ホークス社 総代理店 33 ソーホー・スクエア ロンドン W |
これらの銘刻の上には円形模様で
| 1862年ロンドン万国博覧会 |
下にはマルセル・オーギュスト・ラウーの頭文字を組み合わせた浮き彫りがある。
| MAR |
ラバイエはミニモ通りで1866年から1878年まで営業したが、彼もやはりフランス軍との契約を独占していたサックス社の軋轢に耐えられず、工房をミルローに売却した。
ホークス社はラバイエのイギリス総代理店だった。ラウーのホルンはナチュラル・ホルンで輸入され、ヴァルヴはイギリスで取り付けられた。 19世紀後半ではハンド・ホルンにヴァルヴを付けたり、着脱可能のヴァルヴを装着することが普通だった。 ホークス社のウィリアム・ブラウンは、全てのラウーモデルにすばらしいヴァルヴを取りつけた。
当時の着脱可能ヴァルヴ付きラウー・ラバイエ・ホルンはB♭アルトからCバッソまでの9本の替管やBとB♭バッソ用ハーフ・トーン及びフル・トーンカプラー(連結管)とかなり重たいケースに入ったヴァルヴ類を一纏めにした木箱に入れて使われた。 当時、軍楽隊などではFとE♭の2本の替管と長めのヴァルヴのみというのが普通だった。オーケストラ用のフレンチ・ホルンはヴァルヴ2、3個で、少し短いA管とAから下のE♭までの替管というものが代表的だった。 Aハーフ・トーンや他の替管もあった。2本のスライド管は高めや低めに音程を合わすことができた。
オ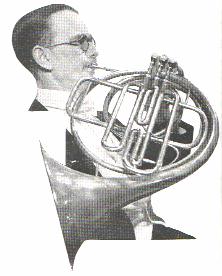 ーブリーはBBC交響楽団のホルン・セクションはすべて他のヨーロッパ製のワイド・ボア(太管)楽器ではなく、フレンチタイプの非常に音の奇麗なナロウ・ボア(細管)仕様のラウーを使うべきだという考えだった。
(逆にロンドン交響楽団のアラン・ハイドは1930年、アレキサンダーのダブル・ホルンを使うことを強く主張していたし、サー・トーマス・ビーチャムのロンドン・フィルハーモニー管弦楽団もドイツ製のワイド・ボア楽器を使用していた。)
ーブリーはBBC交響楽団のホルン・セクションはすべて他のヨーロッパ製のワイド・ボア(太管)楽器ではなく、フレンチタイプの非常に音の奇麗なナロウ・ボア(細管)仕様のラウーを使うべきだという考えだった。
(逆にロンドン交響楽団のアラン・ハイドは1930年、アレキサンダーのダブル・ホルンを使うことを強く主張していたし、サー・トーマス・ビーチャムのロンドン・フィルハーモニー管弦楽団もドイツ製のワイド・ボア楽器を使用していた。)
「月刊音楽レコード」誌1931年7月号の中でオーブリーは次のように述べている。
ドイツのオーケストラの演奏を聴いた聴衆は大概、ホルンの音色が変なユーフォニアムのように聞こえざるを得ない。
オーブリーはB♭管ホルンは音色が良くないとしてイーゴリ公序曲やブランデンブルグ協奏曲第1番などを例外にしてほとんどF管ホルンを使った。また、オーブリーがそのラウー・ラバイエ・モデルで音を外さないのは有名で、1920年代のロンドンの学生たちは、まことしやかに噂しあった。
オーブリー・ブレインは第1ヴァルヴのどこかに木切れを挟んで、この「亡霊」を退治しているんだって!
デニス・ブレインは小さい頃から父の吹くホルンにとても興味を示した。1933年、デニスが王立音楽院に入学する少し前に、父オーブリーは自分が吹いていたのと同じフランス製ラウー・ホルンをデニスに買い与えた。
このF管ラウーでデニスはまだRAF(イギリス空軍中央音楽隊)にいた1943年6月21日、マンチェスターのディーンスゲートにあるホールズワース・ホールでハレ管弦楽団と初のモーツァルトのホルン協奏曲(第4番変ホ長調K.495)を録音した。
このホールはもともとメソジスト教会のもので小編成のオーケストラや室内楽の演奏会が行われていた。当時ハレ管弦楽団のホルン・セクションには1番にリヴィア・ゴランツ(後に有名な出版社を設立)と3番にエニッド・ロパーの2人の女性がいた。首席指揮者はニューヨーク帰りのジョン・バルビローリが就任したばかりだったが、レコーディングには前任のマルコム・サージェントが当たる筈だった。ところがセッションが始まってもサージェントが来ない。 やむなくコンマスのローレンス・ターナーが第2、第3楽章を指揮することになったが非常に良い出来。やっと到着したサージェントは第1楽章を振ったが録音はそのまま完了となり、指揮者名の無い「デニス・ブレインとハレ管弦楽団」というクレジットで発売された。
 デニスが1946年3月27日、アビー・ロード・スタジオでワルター・ジュスキント指揮フィルハーモニア管弦楽団とモーツァルトのホルン協奏曲第2番変ホ長調K.417の録音で吹いた楽器は短いヴァルヴ・スライド付B♭替管を使用したラウー・ミルローである。
デニスが1946年3月27日、アビー・ロード・スタジオでワルター・ジュスキント指揮フィルハーモニア管弦楽団とモーツァルトのホルン協奏曲第2番変ホ長調K.417の録音で吹いた楽器は短いヴァルヴ・スライド付B♭替管を使用したラウー・ミルローである。
指揮者はジョン・バルビローリの予定だったが急病のため、ジュスキントが代役を務めた。
1947年5月21日、キングズウェイ・ホールにおけるシュトラウスのホルン協奏曲第1番変ホ長調作品11のレコーディングでもデニスは古いラウーを使用した。見栄えはともかくデニスのラウーの音色はとても美しく見事な演奏だった。もう一人の偉大なるホルン奏者、故アラン・シヴィルがデニス・ブレインと初めて会った時の思い出を語っている。
デニスは私に吹いている楽器の材質は何だと尋ねてきました。長年使ってきた私の古いフレンチタイプはもうあちこち凹(へこ)みだらけでとても恥ずかしく、しぶしぶ彼に見せたところ、デニスのラウー・ミルローはボロボロで、見比べてみると、私のが組立て台で出来立ての新品に見えたのには驚きました。デニスのラウーはラッパに今まで見たことも無いような凹みがあり、支柱もばん創膏や黒い絶縁テープでぐるぐる巻きでした。
1948年10月10日、南ドイツ、バーデン・バーデンのクア・ザールでデニスは作曲家パウル・ヒンデミットの指揮でモーツァルトのホルン協奏曲第2番を演奏した。使用楽器はF管ラウーだった。この共演はヒンデミットがデニスのために新しい協奏曲を書くきっかけとなった。 ヒンデミットは、音色の軽いB♭管向きの、とてもレガートで、調子が良く跳躍の多い曲を作曲した。しかも終楽章で少しストップ(ミュート)奏法が入る(B♭管のホルンでストップ音を正しい音程で吹くのはとても困難)。そこでデニスは楽器をパックスマン・ホルン店に送って調性(基音)をB♭にした上、ストップ音を上手に出すために、親指でA管に切換えられるようロータリー・ヴァルヴを付けさせた。
ところが修理から戻ってきたラウーはいくつかの音程、とりわけ上のGが不安定だった。それでプロムスのシュトラウスの協奏曲第1番にファーカーソン・カズンズ(b.1917)から40ポンドほどで買った1818年製ラウーを使った。カズンズはヨークシャー州ハダースフィールドのパブでヨークシャー交響楽団の連中と一杯やっているとき偶然BBCによる生中継を聴いたという。
デニス・ブレインのホークス社製ヴァルヴ付きラウー・ラバイエ・ホルンはエディンバラ大学歴史的楽器コレクションで見ることが出来る。 ベルには花文字で次のように刻まれている。
| ラウー セルパン通り、パリ 皇帝陛下、エジプト太守閣下御用達 |
そしてオーブリーのものと同じMARの浮き彫り。
| MAR |
2番目のヴァルヴには
| ホークス&サン/ロンドン/☆/9 |
ヴァルヴ軸と底蓋には
| 19、20、21 |
| ベル | イエローブラス |
| ベル直径 | 278mm |
| ボアサイズ(マウスパイプ) | 12.1mm |
| ヴァルヴシステム | ロンドン、ホークスアンドサン社製ペリネ式3ピストン |
| 調性 | フランス型F管 |
| 可変チューニング・スライド | E♭、F、G、A♭、A |
| マウスピース | リム内径 16.2mm、スロート径 3.7mm |
| 現在の所有者 | グラハム・メルヴィル・メイソン |
Last Updated 2004/6/12