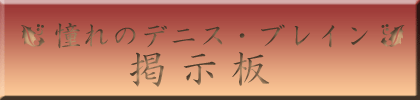
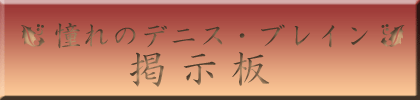
300.コンチェルトシュツック | |
| name: | 大山幸彦 - 2002年12月26日 1時18分13秒 |
昔やりましたが、あれ意外と透明でフーガみたいな曲ですね。 力みをなくすると可憐な曲です。 例のバルボトウ、ベルジェス、デュバル、クルシェのに憧れてやったわけです。 | |
299.今日はクリスマス | |
| name: | 夢中人 - 2002年12月25日 18時47分13秒 |
ですがシッセさんのお兄さんは、デンマークでクリスマス・ツリーを栽培しておられるので、ここのところ農場が相当忙しかったのではと思っています。 木の栽培というと、林業や山を連想しますがクリスマス・ツリーは、畑というか平地で育てられます。デンマークの家庭では毎年ツリーを買い求めると言われるので、クリスマスを祝う習慣の無い夢中人が、一度買ったツリーはどうするんですか?と愚かな質問をしたところ、ツリーは花と同じで毎年新しく買うんだよ、と笑って答えられました。 さて2002年もあと1週間。振り返りますと、今年は自主制作CDに関する色々な出来事を中心にまさに夢中で過ぎた1年となりました。もともと趣味で始めたことですが、やっているうちに大変なことになってしまい、そのたびに直接間接に大勢の方に助けて頂いて、逆にこちらが感動したり多くのことを学ばせて頂きました。本当に感謝の念に絶えません。そしてもうひとつ言えるのが、いまやこのホームページやCDは、間違いなく自分の大きな支えになっている、ということ。大変ありがたいことと思っています。 CDの再発では今までお宝を出してこなかったSONY CLASSICAL UKがひとり元気でした。ビーチャム/ロイヤル・フィルのワーグナー大変良かった。TESTAMENTやDUTTONはネタ切れの感じ。あるいはもうビーチャムやクレンペラー、カラヤンといったビッグネームに頼らない姿勢が必要なのではないでしょうか。一方で最近レーベルを越えた編集や放送ライヴ録音の発掘が増えてきたのは歓迎です。 そんな訳で、何はともあれ、皆様にメリー・クリスマスと良いお年を! | |
298.おまけはブレイン | |
| name: | Favart - 2002年12月21日 0時56分53秒 |
私が初めて買ったブレインのレコードはいったい何で何時だったか?と急に思いたち、自分のレコード・リストを調べてみたところ、何と初めてのレコードは例のケンペorケンペン/ベルリン放送交響楽団のレコードでした。1985年9月16日、新宿の帝都無線(紀伊国屋書店のエレベータを上がった2F入り口にあった)で買っていました。実のところ、このレコードを買った目的はブレインでなく、一緒に入っているドイツのフルートの名手ハンス・ペーター・シュミッツでありました。(シュミッツは「207のBPOのフルート」で書いたようにオーレル・ニコレの前の主席奏者[1943〜1950]です。)シュミッツはレコードがとても少なく、貴重なレコードが出たとのことで飛びつくように購入した分けです。ちなみに、このレコードではシュミッツがA面でブレインはB面なのです!ですから、ブレインはおまけで買ったことになります。しかしながら、私のレコード・リストを見ると、その1週間後の9月23日に今度はカラヤン/POの協奏曲全集を買っています。ブレインのホルンがよほど気に入ったのでしょう。 このレコードを買う前にもホルンのレコードを買っていました。ザイフェルトのホルンでホルン五重奏曲K.407、とK.334(ベルリン・フィル八重奏団)を1984年11月に買っていました。これがはじめて買ったホルンの曲のようです。 グリラーとブレインのK.407に惚れ込んでいるのは、このころの延長のようです。 292で「アダージョとアレグロは何と1回も取り上げられていませんでした。」と書きましたが、元々ホルンとピアノのための曲で、オーケストラでの演奏はアンセルメのレコード(アンセルメ編曲)のみで、一般的ではないのでしょう。 | |
297.シューマン/4本のホルンのための協奏的作品、作品86 | |
| name: | 夢中人 - 2002年12月20日 21時44分54秒 |
シカゴ響の最強ホルン・カルテットによる演奏はさぞや素晴らしかったのではと思います。またまた手前味噌で大変恐縮なのですが、1984年12月16日、所属するバンド(明石高校OB吹奏楽団)がこの曲にチャレンジしたことがあります。 私は当時既にレギュラー・メンバーではありませんでしたが、なかば無理矢理に伴奏の1番ホルンを吹いてこの珍しい曲の実演を体験しました。曲は冒頭からド派手なファンファーレで始まり、独奏1番ホルンが第1楽章のそれも終り近くで実音A’という信じられないようなハイノート(こういう言い方はトランペットにこそ相応しいですが)を普通のB♭管で吹くのを殆ど感動の思いで聴(吹)いていました。 舞台にズラリと並んだ4人の若武者たちは、両端楽章のまさに「空中戦」を止まることもなく一見クールに吹き切りましたので、後輩ながら天晴れ、よくやったありがとうと心からの拍手を贈りました。 因みにこの曲は、1849年の作曲。同じ年に「ホルンとピアノのためのアダージョとアレグロ変イ長調作品70」「4本のホルンと男声合唱のための狩りの歌作品79」も作曲されました。いずれもドレスデンのハイレベルなホルン奏者に啓発されて生まれたといわれます。 | |
296.ダムの演奏会は | |
| name: | CATO - 2002年12月20日 7時06分25秒 |
モーツァルト室内管弦楽団という関西の団体で、指揮者は門良一でした。で、1998年だったと思います。 ところで、掲示板に新人が出てきませんね。う〜ん、私なんかの思いつきのいい加減な書き込みが悪影響を与えているのかも。 | |
295.演奏会データ | |
| name: | Favart - 2002年12月19日 22時24分19秒 |
1927-1981の交響楽団、国内演奏会データより <ダムのモーツァルトの協奏曲第3番> 1979.4.24 日フィル #311 渡辺暁雄 1981.3.25 名フィル #76 外山雄三 <ダム、同第4番> 1981.3.24 日フィル #331 山岡重信 <タックウェルのモーツァルトの協奏曲第2番> 1967.11.8 札響 #67 荒谷正雄 <タックウェル、同第3番> 1977.2.25 読響 #128 フォルカー・レニッケ <近藤望のR.シュトラウスの協奏曲第1番> 1973.4.23 大フィル #107 朝比奈隆 ダムのモーツアルト協奏曲全4曲は見つかりませんでした。 メジャーなオーケストラでなく室内管弦楽団の伴奏かもしれません。 指揮者が分ると出てくるかもしれません。 ちなみに、ダムとタックウェルのR.シュトラウスの協奏曲は 第1番 1967.11.8 札響 #67 荒谷正雄 タックウェル→上記モーツァルト2番と同じ日 1979.4.24 日フィル #311 渡辺暁雄 ダム→上記モーツァルト3番と同じ日 第2番 1977.2.26 京響 #192 若杉弘 タックウェル モーツァルト、R.シュトラウスともに演奏者はほとんどがドイツ、オーストリア系で、残念ながらフランスの奏者は見つかりませんでした。
| |
294.音と聞く場所 | |
| name: | CATO - 2002年12月19日 9時26分28秒 |
音の聞こえ方については、論じるとエンドレスになりますね。 私は大阪シンフォニーホールでペーター・ダムのモーツアルト協奏曲全4曲を聴きましたが、期待通りの素晴らしい音と出来でした。ただし、休憩時間には、音が広がりすぎて変だったと言う人の話も聞こえてきました。座る場所でこれほど違います。あと、かなり前、近藤望がフェスティバルホールで大フィルとRシュトラウス1番を演奏したとき、あれっと思うほど独奏部分が小さく聴こえた経験をしています。たしかこの時は、1階奥の右隅の変な安い場所で聴いたような気がします。3階席の友人はよかったを繰り返していたのに。同じCDでも再生装置、部屋、音量等でかなり違うんでしょうね。 思うに、実演は「酸化」に一方的に身を任せることで、席を換えることも、聴きなおしもできません。一方、録音鑑賞は「還元」の作業で、終わった現象のエンドレスな再現作業です。無限の薀蓄と論争を産み出しますね。などと書くと、酸化・還元??と言われそうですが。これについては、追々展開しようと思っています(と同じことを、20年も前に友人に言ったきり発展なしですが)。このような話題になると、吉田秀和とかグレン・グールドの、再生芸術についての意見を再読したくなります。でも、本棚のどこにあるのか、はたまたダンボールの底か? | |
293.荒々しい音 | |
| name: | 夢中人 - 2002年12月19日 0時06分59秒 |
>昔、東京文化会館でペーター・ダムのモーツァルトを聴いたことがあります。レコードと同じ音がしてとても良かったです。逆にレコードと違っていたのがバリー・タックウェル。モーツァルトやシュトラウスのLPから大きくて荒っぽい印象を持っていましたが、実際はとても繊細な感じでした。 デニス・ブレインのライヴ録音が良い状態で聴けるようになって、ヘルベルト・フォン・カラヤンのLPと寸分違わない、或いはさらに素晴らしいなどと感じたりします。でも1950年より以前、ラウー・ホルンを吹いていた頃、はちょっと違うようです。 国際ホルン協会(IHS)誌『ホルン・コール』1991年10月号、デニス・ブレイン生誕70周年特集でサー・トーマス・ビーチャム/ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の1950年USAツアーを聴いたことのあるアメリカ人のホルンの先生が「デニスの音は明るいコルネットとトロンボーンの“合いの子”みたいだったけれども信じられないほど正確だった」と発言したのに注目しました。 1948年南西ドイツ放送でのヒンデミットとのモーツァルト/協奏曲第2番(HPE CD02)やビーチャム/RPOのモーツァルト/ディヴェルティメント第2番ロ長調 K.131(Dutton CDLX 7037)などで聴かれるデニス・ブレインの音は、ピストン・ヴァルヴのラウー・ホルンによるもので、以後のアレキサンダー・ホルンの美しい音に慣れた耳には驚く程荒々しく響くことがあります。 | |
292.ついでに、もうひとつ(シューマン) | |
| name: | Favart - 2002年12月18日 23時39分37秒 |
「1927年〜1981年の日本国内オーケストラ演奏会記録」ではアダージョとアレグロは何と1回も取り上げられていませんでした。4つのホルンの方は1回だけ演奏されています。 1977.611小沢征爾/新日フィル(#50定演)、Hornはデイル・クレヴェンジャー、リチャード・オールドバーグ、トマス・パウエル、ノーマン・シュヴァイカート「1927年〜1981年の日本国内オーケストラ演奏会記録」はなかなか重宝しています。何か知りたいことがあれば、お調べします。海外の来日オケも含みます。 | |
291.理想の音 | |
| name: | Favart - 2002年12月18日 23時14分10秒 |
|
演奏者にとっても聴衆にとっても理想の音は人それぞれですね。「ブレインの音は左程魅力的ではないし、いわゆる“ロマンチック”な音でもない。」という言葉はあくまでIb Lansky-Ottoの個人的な嗜好で、一般的な話として言っているわけではないでしょう。でも、他の奏者を否定的に言うのはちょっと・・・と思います。 シューマンの4本のホルンはZ.&B.ティルシャル,スハーネク,ディヴォキーでノイマン/チェコ・フィルもあるそうです。ついでにアダージョとアレグロはホルンよりもチェロでの録音が多いのですね。カザルスのホワイト・ハウス・コンサートに入っているのをはじめて知りました。ブヤノフスキーの1963年の録音も国内CDで1991年に出ていました。(ベートーヴェン、ロッシーニと一緒) | |
