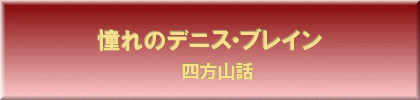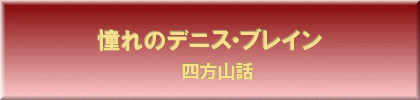|
| 第190話「浅田真央選手優勝おめでとうございます」 |
  先日ロシアのソチで開かれたフィギュア・スケート・グランプリファイナル(世界一決定戦)で、復活優勝した浅田真央選手。腰痛を押しての出場だったとのことで、本当におめでとうございました。 先日ロシアのソチで開かれたフィギュア・スケート・グランプリファイナル(世界一決定戦)で、復活優勝した浅田真央選手。腰痛を押しての出場だったとのことで、本当におめでとうございました。
ご本人も好きなプログラムと言われていた「白鳥の湖」。有名な「情景」を始めとする4曲から構成されていました。オーボエの音色がウィンナ・オーボエのように聞こえたのですがどこのオーケストラでしょうね。ブレイン時代のフィルハーモニア管弦楽団の録音ではマルケヴィッチのものが3曲を含んでいてとてもダイナミックな演奏です。
1. No.10 Scéne (Moderato)
2. No.5b Pas de deux (Andante)
4. No.5d Coda
|
2012年12月15日 10時38分52秒
| |
| 第189話「ペレアスとメリザンド」 |
  デジレ=エミール・アンゲルブレシュト(1880-1965)とフィルハーモニア管弦楽団によるドビュッシーの歌劇の初放送録音(1951年6月1日BBC)!これまでブレインの2冊の伝記はおろか、BBCアーカイブや大英図書館(ナショナル・サウンド・アーカイブ)もその存在を伝えていなかった奇跡のような音源のCD化。発売日(10/29)から程なくしてやってきました。 デジレ=エミール・アンゲルブレシュト(1880-1965)とフィルハーモニア管弦楽団によるドビュッシーの歌劇の初放送録音(1951年6月1日BBC)!これまでブレインの2冊の伝記はおろか、BBCアーカイブや大英図書館(ナショナル・サウンド・アーカイブ)もその存在を伝えていなかった奇跡のような音源のCD化。発売日(10/29)から程なくしてやってきました。
これまでブレインの録音を追求する余りに、そのほかの音楽に耳を貸さずにきたわけで「ペレアスとメリザンド」は木下さんが下さった五味康祐の『西方の音』で「読んだ」くらいで聴いたこは一度もありませんでした。歌詞の日本語訳は、岩波文庫の対訳『ペレアスとメリザンド』を参照することに。音もそんなに悪くなく、毎日少しずつ聴き進んでいます。
リブレット・歌詞対訳(英語)
|
2012年11月14日 21時58分59秒
| |
| 第188話「ホーン・ベルト・ブギ」 |
デニス・ブレインの選んだ8枚のレコードとてもセンスが良く、繰り返し聞いています。特に「ホーン・ベルト・ブギ」楽しいですね。曲はミッチ・ミラー(1911-2010)のアイデアによりアレック・ワイルダー(1907-1980)が1951年に作曲した4本のホルンのためのジャズ組曲の第1曲。
レコードは1951年9月録音。演奏はホルンが、ヨゼフ・シゲティと入れたブラームスのトリオで知られるジョン・バローズ (1913-1974) 、ジャズ・ホルン奏者のジェームス・バフィングトン、レイ・アロング、作曲家でもあるガンサー・シュラー(b1925)。あとハプシコードのスタンレー・フリーマン、リズムのミッチ・ミラーといった顔ぶれです。
ところで「ホーン・ベルト・ブギ」って角(で作った)ベルトのブギでしょうか?興味津々なんですけど楽譜は絶版で手に入りませんでした。ワイルダーを讃えるサイトからもう1曲!Mitch Miller / Conversation Piece by Alec Wilder
FOR HORNS AND HAPSICHORD
1. Horn Belt Boogie
2. Serenade For Horns
3. Singing Horns
4. Horns O' Plenty
|
2012年10月20日 08時15分20秒
| |
| 第186話「1954年9月9日、エディンバラにおけるフィルハーモニアの演奏会ライブ」 |
  1954年9月9日、アッシャー・ホールにおけるグイド・カンテッリとフィルハーモニア管弦楽団(PO)の演奏会録音が遂に世に出ました。「世界で最もレコード録音されたオーケストラ」POでもライブ盤は大変珍しく、数える程しかありませんので貴重です。ICAのウェブサイトでサンプル(ドビュッシーの「海」から「風と海との対話」)を聞くと、POの演奏はとてもシンフォニックでフランスのオーケストラで擦り込まれたドビュッシー演奏のイメージとは随分違います。「海」は4日後の9月13日、またその他の楽曲も全てレコード録音が行われており、比較できるのも愉しみですね。 1954年9月9日、アッシャー・ホールにおけるグイド・カンテッリとフィルハーモニア管弦楽団(PO)の演奏会録音が遂に世に出ました。「世界で最もレコード録音されたオーケストラ」POでもライブ盤は大変珍しく、数える程しかありませんので貴重です。ICAのウェブサイトでサンプル(ドビュッシーの「海」から「風と海との対話」)を聞くと、POの演奏はとてもシンフォニックでフランスのオーケストラで擦り込まれたドビュッシー演奏のイメージとは随分違います。「海」は4日後の9月13日、またその他の楽曲も全てレコード録音が行われており、比較できるのも愉しみですね。
ICA Classics
ブレイン時代のフィルハーモニア管弦楽団演奏会録音
|
2012年09月08日 09時25分49秒
| |
| 第185話「メーカーズ・オブ・フィルハーモニア / アナトール・フィストラーリ」 |
  ジョン・ハントの「メーカーズ・オブ・フィルハーモニア」(1996年出版)は、オーケストラの創設初期に関わった、ともすれば忘れそうになりがちな指揮者を集めたディスコグラフィーです。彼はその前書きで Testament がマルコやクレツキ、マタチッチの1枚ものCDを出してくれたけれども、ガリエラやドブロウエンは伴奏指揮したものばかり。折から出されたフィルハーモニアの50周年記念3枚組CDはカラヤンやクレンペラーらビッグネームによる既出商業録音ばかりで一体アーカイビストは何考えてんだ!みたいな不満を述べていました。 ジョン・ハントの「メーカーズ・オブ・フィルハーモニア」(1996年出版)は、オーケストラの創設初期に関わった、ともすれば忘れそうになりがちな指揮者を集めたディスコグラフィーです。彼はその前書きで Testament がマルコやクレツキ、マタチッチの1枚ものCDを出してくれたけれども、ガリエラやドブロウエンは伴奏指揮したものばかり。折から出されたフィルハーモニアの50周年記念3枚組CDはカラヤンやクレンペラーらビッグネームによる既出商業録音ばかりで一体アーカイビストは何考えてんだ!みたいな不満を述べていました。
そんなハントさんの溜飲を下げる1枚がスイスの Guild が出したアナトール・フィストラーリのロシア名曲集。ステレオLPからの復刻ですがまずまずの状態です。何よりチェレプニンがバレエのために編曲したボロディンの夜想曲(弦楽四重奏曲第2番第3楽章)でデニス・ブレインがソロを吹いてるのが素晴らしいです。
メーカーズ・オブ・フィルハーモニア
アルチェオ・ガリエラ(1910-1996)
ワルター・ジュスキント(1913-1980)
パウル・クレツキ(1900-1973)
ニコライ・マルコ(1888-1961)
イザイ・ドブロウエン(1891-1953)
ロブロ・フォン・マタチッチ(1899-1985)
エフレム・クルツ(1900-1995)
オットー・アッカーマン(1909-1960)
アナトール・フィストラーリ(1907-1995)
ジョージ・ウェルドン(1908-1963)
アーネスト・アーヴィング(1913-1995) |
2012年08月19日 08時11分00秒
| |
| 第184話「ロンドン!ロンドン!ロンドン!」 |
  いよいよですね。そんな中、英国Sommの新譜、サー・トーマス・ビーチャムとロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団(RPO)によるサン=サーンス(1835-1921)の交響曲第3番ハ短調「オルガンつき」を落手しました。残念ながらデニス・ブレイン退団後の録音ですが、1954年10月20日、ロイヤル・フェスティバル・ホールにおけるライブ録音でデニス・ボーハンによるオルガンの壮大な響きを体感できます。 いよいよですね。そんな中、英国Sommの新譜、サー・トーマス・ビーチャムとロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団(RPO)によるサン=サーンス(1835-1921)の交響曲第3番ハ短調「オルガンつき」を落手しました。残念ながらデニス・ブレイン退団後の録音ですが、1954年10月20日、ロイヤル・フェスティバル・ホールにおけるライブ録音でデニス・ボーハンによるオルガンの壮大な響きを体感できます。
曲は元々ロンドン・フィルハーモニー協会の委嘱により作曲され、サン=サーンス自身の指揮する同協会が1886年5月に初演したもの。このCDのサブ・タイトルは「知られざるビーチャム」BYWAYS OF BEECHAM とありますがビーチャムは、ご存知のとおりフランス音楽が大得意。その自叙伝『混じり合う鐘』A Mingled Chime(1944)に、1913年クイーンズ・ホールにおけるサン=サーンスの音楽祭で交響曲第3番を指揮したときのエピソードを披露しています。 ここ数年あの有名なフランスの作曲家(サン=サーンス)は、眠くなるようなテンポを好むようになり、それがしばしば彼の解釈者たちを当惑させる原因となっている。今回彼はリハーサルにしばしば姿を見せたが、それが逆にますます演奏者たちにプレッシャーを与えてしまい、もしこれが良い方向に作用しないと大失敗となってしまう。そこで私は本番で故意にアクセントを誇張し、速度に関する指示をあまり目立たないように変えて精一杯の感動を生むよう全力を挙げた。
その日の夕食で彼に作品の演奏に満足しているか尋ねると、彼はまるで輝くような慈悲深さで答えた「私が君の解釈についてどう思っているかと言うのかね」私は彼の考えを聞く限り、きっとご満足いくものではないのでは、と言うと「ああ若き友よ、私は長い間生きてきて、オーケストラのシェフをみんな知っている。彼らには2種類あってね。音楽が速すぎるのと、遅すぎるのと。3番目は無いんだよ」
|
2012年07月27日 06時53分18秒
| |
| 第183話「FB / Dennis Brain A Life In Music」 |
デニス・ブレインの新しい伝記作家スティーヴン・ギャンブルさんが本の販売促進のためにフェイスブックを作りました。他では見ることのできない可愛い子供時代の写真や唯一のカラー写真などを公開されています。フェイスブックに参加している方は、是非彼とお友達になって「いいね!」して下さい。
|
2012年07月22日 12時59分48秒
| |
| 第182話「グイド・カンテッリ / 指揮台の燃える天使」 |
  グイド・カンテッリ(1920-1956)とフィルハーモニア管弦楽団の録音は、Testamentがレーベルの発足当初から1枚1枚CD化を重ねた6枚とEMIのartist profileシリーズの2枚組がその全てでした。この限定盤ボックスはそれらからメンデルスゾーンのイタリア(1951年録音)を除いた8枚に、ダフニスとクロエや運命の未発表リハーサル録音を含むオーディオ・ドキュメンタリー1枚を加えた計9枚を内容としています。ブラームスの3番やチャイコフスキーの悲愴などは古いEMIのリマスターが使用されていますが、いずれもブレインが参加していますのでお勧めです。 グイド・カンテッリ(1920-1956)とフィルハーモニア管弦楽団の録音は、Testamentがレーベルの発足当初から1枚1枚CD化を重ねた6枚とEMIのartist profileシリーズの2枚組がその全てでした。この限定盤ボックスはそれらからメンデルスゾーンのイタリア(1951年録音)を除いた8枚に、ダフニスとクロエや運命の未発表リハーサル録音を含むオーディオ・ドキュメンタリー1枚を加えた計9枚を内容としています。ブラームスの3番やチャイコフスキーの悲愴などは古いEMIのリマスターが使用されていますが、いずれもブレインが参加していますのでお勧めです。 |
2012年06月23日 10時05分21秒
| |
  
|
|