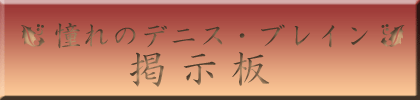
前へ | 過去ログメニューへ|次へ
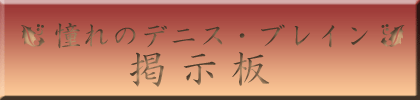
600.あの頃君らは若かった | |
| name: | CATO - 2003年10月18日 19時51分25秒 |
「597」の「曲の終り近くのデニス・ブレインによる変ホ長調の音階の優雅さは誰にも真似が出来ないでしょうね!」に全く同感です。そしてもう一箇所、一楽章の終わり近くの鋭い駆け上がりも。録音時カラヤン46歳、ブレイン33歳。カラヤンもびっくりのブレイン節で駆け上がって、カラヤンと録音中にニッコリ挨拶、という情景はそんなに無理の無い想像では?「偽作」よ、有難う。 | |
599.フィビヒ | |
| name: | K - 2003年10月18日 16時25分17秒 |
| url: | http://www.karajan.info/ |
こんにちは、こちらでははじめまして。 探し方が悪いのかも知れませんが、こちらのサイトで見つかりませんでしたので、念のためお知らせしておきます。 ブレインの初出音源収録という触れ込みのCDがSYMPOSIUMからアナウンスされています。 フレデリック・サーストン〜保管&ライヴ録音集 1948-1952(SYMPCD-1259) http://... ブレイン参加曲はフィビヒのピアノ、ヴァイオリン、チェロ、クラリネットとホルンのための五重奏曲作品42だそうです。
| |
598.ご教示ありがとうございます | |
| name: | CATO - 2003年10月18日 12時07分35秒 |
偽作については背景資料もあったりして、やはり慎重に探索が進んでいるんですね。音楽学、音楽歴史学のような分野では大胆な意見を述べて、その後にこれを覆す実証的反論が出た場合、学者として大ダメージなんでしょう。反面「独奏部のみがモーツァルトのよるもので、管弦楽は後世の者が書き加えたもの」と推測することで身を立てているロバート・レヴィン氏たちをうらやんでしまいます。 | |
597.K.Anh.9(297B) | |
| name: | Favart - 2003年10月18日 8時57分26秒 |
海老澤氏も「現在(1991年東京書籍刊)のところその真偽についてはまだはっきりと結論を出すことはできないと言えよう。」とのことです。 『パリを訪れていたモーツァルトは当地で名高い公開演奏会「コンセール・スピリチュエル」の支配ル・グロにすすめられて協奏交響曲を1曲作曲した。この曲は当時パリに滞在していたマンハイム宮廷楽団のヴェンドリンク(fl)、ラム(ob)、リッター(fg)、それにパリで活躍していたシュティッヒ(hrn)を独奏者として「コンセール・スピリチュエル」で演奏するために書かれたのであったが、なぜか演奏されずに終わり、ル・グロに売り渡された自筆譜も失われてしまった。演奏されなかった理由についてモーツァルトは父宛の手紙の中で「当地のイタリアの作曲家カンビーニがからんでいると思います。」とのことで、実際、モーツァルトと同じ編成をとるカンビーニの新作の協奏交響曲が同じ独奏者たちにより演奏された』とのことです。 『19世紀半ばに発見された「オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットのための協奏交響曲K3.297b(Anh.C.14.01)は、この失われた協奏交響曲の編曲であるとも考えられている。ロバート・レヴィンはモーツァルト自身が編曲したものとみなしているが、現存するかたちは、独奏部のみがモーツァルトのよるもので、管弦楽は後世の者が書き加えたものと推測している。そしてこの編曲版をもとにフルートを含む原曲のかたちの復元を行っている』とのことです。 どこかからひょっこり自筆譜が出てくるとよいのですが。グロめが!
| |
596.贅沢な審査員 | |
| name: | CATO - 2003年10月18日 2時35分25秒 |
金曜の夜は早く一旦寝るのがクセで、昨夜はカラヤン/ブレインのモーツァルトの協奏交響曲を気分よく聴きながら、なぜこれが「偽作」なのかなと改めて思いつつ寝入りました。起きだして掲示板を見ると補筆の話題があって驚きました。私がネット(ただし日本語の範囲)で見たところでは、協奏交響曲は真贋論争継続中とのことでした。また、関連資料の判断が主体で、曲の作りに則してこういう理由で真/贋作であるというような意見は見つかりませんでした。私がこの曲が「偽作」とされていると知ったときの感想は、余りにモーツァルト的過ぎるのかな、ということでした。技術のある人がモーツァルトのエキスを集めた曲、と言われれば、そう信じてしまうほどモーツァルト的というのが私見です。海老澤敏氏の意見が知りたくなりました。 ということで、ネットついでに今度はAmazonの1分試聴に回ってホルンの聴き比べを、モーツァルト第二番の第三楽章でしました。大家を審査する気分です。今夜改めて好みであると判ったのがヴラトコヴィチで、第一位でした。なんともバランスがいいです。音色も活舌も好みでした。彼のは買うことにしました。あと、別格の甘いクリーミーな音色のダムに特別賞です。彼はマリナーのオーケストラと競演していますが、イギリス流のホルンの音色に親しんできた楽団員にはさもや大きな衝撃を与えただろうと想像できます。ブヤノフスキー、パイヤット、クレベンジャー、シヴィル、ザイフェルト、タックウェルなんかも次々登場で贅沢な気分でした。 | |
595.絶筆の補筆 | |
| name: | Favart - 2003年10月17日 23時07分26秒 |
早速NAXOS盤を聞いてみました。あれっ!と思うような箇所がいくつかありました。 慣れというものは恐ろしいものですね。ジュースマイヤーの補筆の部分もモーツァルト作曲と思い込んでいるわけですから。 絶筆の補筆ということではレクイエムK626が話題に上がる事が多いですね。こちらは、フランツ・クサヴァー・ジュースマイヤー(+ヨーゼフ・レーオポルト・アイブラー)、フランツ・バイヤー、リチャード・モーンダーの御三方の補筆があり、ジュースマイヤー版が生身のモーツァルトから完成の指示を受けていたとのことで標準版になっています。 海老澤敏氏は例の本の中でモーンダー版(1986年)に関連して「モーツァルトと縁もゆかりもない20世紀人が補筆者になり代わろうとする試みは、いかに精微な作曲理論の裏付けがあろうと、傲慢のそしりは免れまい。」と記していています。気持ちはわかります。 1791年7月26日フランツ・クサヴァー・モーツァルト誕生(4男) 1791年12月5日アマデウス没 モーツァルトは4男クサヴァー・モーツァルトがコンスタンツェとジュースマイヤーの子供であったことを知っていたのかどうか気になるところです。 ところで、モーツァルトのホルン協奏曲は関東地方ではNHKラジオの交通情報のBGMとして時々登場します。渋滞でいらだつ気持ちをホルンの響きが鎮めてくれる効果があるのでは?K.412の第1楽章だったと思います。 | |
594.モーツァルト/第4(1)番ニ長調 K412、K514(ジュスマイヤー編) | |
| name: | 夢中人 - 2003年10月17日 8時22分00秒 |
Favartさまが587で触れられたモーツァルトのいたずら書きで有名な協奏曲第1番。昔から第1楽章に登場する2本のファゴットが第2楽章には無いのは妙だとか、アンダンテ楽章が何処かにある筈だとか、なんで他にはあるカデンツァが無いの?とかとかく疑問の多い曲でした。 でも何となく40年ほども過ぎて実はいわゆる4曲中の最後の曲だったのとモーツァルトがロイトゲープを憐れんだのはいたずら書きだけではなく調性を変ホ長調からニ長調に半音下げたという話には天国のデニス・ブレインも驚いたと思います。 モーツァルトの絶筆を自由に改作したようなのが現在一般に聞かれるジュスマイヤー版ですが、イギリスのジェフリー・ハンフリーズがモーツァルトの草稿をもとに編曲したものをマイケル・トンプソンが吹いたNAXOS盤を聴くと全く別の曲なのに二度驚くのではないでしょうか。 そのブレインが有名なカラヤンとのスタジオ録音のほかに現代のロイトゲープよろしくナチュラル・ホルンを吹いて演奏した記録(1955年7月23日BBC第3放送)があります。そこでブレインが吹いた1818年製ラウーは1947年か1948年にファーカソン・カズンズがデニス・ブレインに売り渡したもので1948年、ロイヤル・アルバート・ホールでR.シュトラウスの協奏曲第1番の演奏したものと同じです。 | |
593.お宝に感激! | |
| name: | Favart - 2003年10月15日 0時16分53秒 |
特に上段のSP2組とBISのLPはすばらしいコレクションですね。BISのモーツァルトは是非でCD復刻してもらいたいと思います。 ブリテンのセレナーデは2種類お持ちのようですが、黄色と赤の違いは何でしょうか?ちなみに私のは赤紫色でサンプル盤です。この頃のデッカのモノラルLP(LXT)はとてもしっかりした音で気に入っています。 ケンペorケンペンのモーツァルト(日本盤)はレアかと思っていましたが最近なんと古本屋で100円で売っていて思わず買ってしまいました。これで3枚目なのですが・・・。ほとんど病気と言ってよいでしょう(裏面のハンス・ペーター=シュミッツのフルートもGOOD!)。ブレインがオルガンを演奏した「カヴァレリア・ルスティカーナの間奏曲」が入った「間奏曲集」(日本コロムビアXL-5111)も少し前に100円で見つけました。(貧乏性なのです)
| |
592.ソロ・アルバム・コレクション | |
| name: | 夢中人 - 2003年10月13日 23時39分32秒 |
デジカメを買いましたのでデニス・ブレインのレコード・ジャケットを撮影してみました。初めてなのでなかなかうまく撮れませんでした。しかもコレクターと言われながらレコード盤は19点しか持っていません。まったくお恥ずかしい限りです。でも殆ど木下さんのご好意で頂戴したものなので皆さんにもご覧頂きたく思います(→ここ)。 | |
591.しっくりくるということ | |
| name: | CATO - 2003年10月12日 23時56分47秒 |
Favartさんご指摘の演奏を聴きくらべできず歯がゆいです。 『奇跡のホルン』P259に、「フランスの聴衆はデニスのホルン演奏のスタイルをあまり高く評価していなかった。(同時に、デニスにとってもフランス流の演奏は率直に言って好みではなかった。)」とあるのは判るような気がします。例えば、モーツァルトの5重奏を、フランス系奏者とブレインで聴けば、これらは別物です。そして、英仏の聴衆も音楽院の先生方も、長年にわたってこれこそが我らのモーツァルトと納得しているんでしょう。どういう味付けをしようがモーツァルトという素材が別格なんですかね。 仮に、浄瑠璃三味線が日本発祥ながら、英仏にもそこそこ長い伝統があって、国々で音色や奏法が分化していて、そういう状況で本家日本人が、どうもイギリス流三味線は浄瑠璃の情緒にはしっくり来ないと感じたようなことを、ブレインとフランス奏者達はお互い感じていたんでしょうか。音楽の好みと伝統とは奥が深い。そしてやはり日本は西洋音楽の歴史が浅いなあ。 | |
