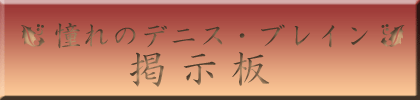
前へ | 過去ログメニューへ|次へ
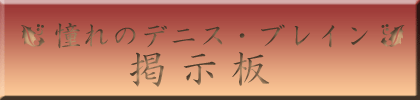
510.1954年10月7日 | |
| name: | 夢中人 - 2003年07月05日 16時34分17秒 |
先日ロシアからやってきた高校生デュオが歌番組にオープニングまで出演しながら、何が気に入らないのか番組途中で帰ってしまう「事件」がありました。半ば話題作りのための騒動と思いつつデニス・ブレインの事件を連想させてくれました。 最近ではピーター・ヘイワース著「オットー・クレンペラー〜その人生と時代 第2巻、1933−1973」(ケンブリッジ大学出版、P1996)にその事件が記述されています。 「10月5日と6日、ジュピター交響曲が録音。翌7日の午前中はデニス・ブレインとヒンデミットのホルン協奏曲の収録する予定。レッグが4年前にこの作品を初演をしたブレインにレコーディングを依頼したものだった。 クレンペラーは伴奏に同意したもののスコアをよく判っていなかった。昼休みにブレインはクレンペラーの遅いテンポと絞まりのないリズムについてレッグに不満を申し出た。クレンペラーがこのテンポを変えることを断ったため、常々レッグが「最も紳士的な男」と評するあのブレインが録音を完了させる筈の午後のセッションに来ることを拒んでしまった。 騒ぎの後、ロッテ(クレンペラーの娘)が父の今後のフィルハーモニアとの関係に不安を感じ、蒼白な顔でレッグのオフィスに突然やってきた。同じくトラブルを避けたいと望んだレッグはホルン協奏曲を止めてヒンデミットの組曲「高貴なる幻想」にすることを提案した。全ての面目が保たれ、ヒンデミットの組曲とともにモーツァルトの交響曲第29番、ブラームスのハイドンの主題による変奏曲が何事も無かったように録音完了した・・・」 (ご参考) ヒンデミットあれこれ 参考盤は下記でマーシャルの「レコードのデニス・ブレイン」ではいずれもデニス・ブレインがいないとされています。 | |
509.ヴェスコーヴォとバルボトゥ | |
| name: | goshikinuma - 2003年07月02日 22時43分32秒 |
Favartさんはじめまして 現在LPを聴いていますが、レコード棚を部屋の隅に眠らしていたものですから、ジャケットにカビが生えていました。タリアーニのハイドンはジャケットがふにゃふにゃでした。レコードのカビは絞ったガーゼで吹いてOKですが、がんこなものはウェットティシューでおとします。 ところでヴェスコーヴォですが、モノラルの音とステレオ録音のモーツァルトの音は全くちがいました。もう30年も聴いていませんでしたから、その違いに驚きでした。ヴェウコーヴォの音はやはり明るく強烈なヴィブラートが特徴と思いますが、パイヤールとのステレオのモーツァルトはドイツ系のロータリーヴァルブのホルンを吹いていますので、かつての音色とは似ても似つかぬものです。これは物足りませんでした。ジュスタフレといわれてもわかりません。 そのあとで聴いたバルボトゥのモーツァルトは遅めのテンポながら明るく楽しいものでした。今日はフランスARIONのレコードを聴きました。べートーヴェンとケックランのソナタ、シューマンのアダージョとアレグロですが、とても遅いベートーヴェンです。こんなに遅くていいのかなと思うほど別の音楽がなっていました。バルボトゥの明るい音は癒されます。R・シュトラウスの2番、ウェーバー、ハイドンの2つのホルンと聴きましたが、デニス・ブレインとおなじように音楽家だなとつくづく思いました。明日はシューマンの4本のホルンをかけたいと思います。 今日は1枚ティルシャル兄弟ほかのシューマンの旧録音を聴きましたが、5人のホルンソリストでの録音です。これがとても楽しめました。やってくれるねという演奏でした。 | |
508.LPレコード | |
| name: | Favart - 2003年07月01日 23時33分59秒 |
goshikinumaさま、はじめまして。 PERENNIALのレコードは今だからこそ入手できたのだと思います。30年前の輸入盤は国内盤よりかなり高く、なかなか手が出ませんでした(私はgoshikinumaさまと同世代です)。今では大量の中古輸入盤が日本に流れ込み、比較的レアなものでも安く手に入るようになったと思います(一部国内通販業者は別として)。 ブレインのレコードは東京でgoshikinumaさまの購入価格の約1/3で入手できました。ちなみに、欧州コンサート・ホール盤のブランデンブルク(ブレイン2回目の録音、CD未復刻)などもインターネットで2枚で4ドル+送料で入手できました。また、PERENNIALのレコードは現在15ドルで売りに出している海外HPがあります。 良い時代になったと思います。 | |
507.ペレニアルのLP | |
| name: | goshikinuma - 2003年06月30日 10時58分37秒 |
今でも入手できたというのにはびっくりです。私は30年前確か神田の店かと思いますが「かっこう」というレコード屋さんがあって、そこで買った値段が3800円という高価なものでした。私のコレクションでは1枚の値段としては最も高価なものでした。ですから滅多にかけられないレコードでした。解説もなくブルーのジャケットに小さく曲名と演奏家が書かれた紙が貼り付けてあるなんとも半端なレコードでしたが、Dennis Brainの文字がとても大きく感じられたものです。 初めて聴くシューベルトの「流れの上で」は当時レコードが無くて、曲名の和訳ができませんでした。この曲をシュライヤーとダムの演奏で聴いてなるほどこれかと分かりました。それにしてもブレインはあまい響きでシューベルトを歌っていました。BBC盤よりもゆったりと歌っていますので好きです。 ブラームスはBBC盤LPと録音は同じですが、私のテイチク盤LPよりも音はいいと思います。レベルも違いました。これは聴きくらべましたのでよく分かります。そういえばテイチク盤のモーツァルトの五重奏はBBCのCDよりもテンポがやや遅めでした。共演者の違いはわかりましたが、データを見たのは20年ぶりくらいでしたからびっくりしました。なにしろCD聴くようになりましたらLPはほんとのお蔵入りでしたので、まさか音を出すとは思わなかったのです。今や毎日LPばかり聴いています。今日聞いたミロシュ・ペトルのモーツァルトはまさにボヘミアのホルンの代表のような音でした。演奏も良かったです。 | |
506.新発見録音ふたつ | |
| name: | 夢中人 - 2003年06月29日 20時58分33秒 |
大英図書館ナショナル・サウンド・アーカイヴのオンライン・カタログによりますとボイド・ニール管弦楽団によるブランデンブルグ協奏曲の新発見録音が存在するようです。 BBC放送の為に1947年に全曲収録されたうちの2回分。独奏者にはデニス・ブレイン、オーボエのレオン・グーセンス、トランペットのジョージ・エクスデールら。1993年3月4日、BBCラジオ3でリンドン・ジェンキンスの解説により第2、第6そして第1の3曲が放送されたとか。 このほか同カタログでケネス・エセックスのホルン協奏曲初演(1955年4月21日)時の録音の存在も確認されています。 | |
505.ルイス、ラッシュとのシューベルト「流れの上で」 | |
| name: | Favart - 2003年06月28日 23時38分14秒 |
シューベルトのテノール、ホルンとピアノのための「流れの上で」はピアーズ、ミュートン=ウッドとの録音がBBCのCDで復刻されていますが、未復刻らしきルイス、ラッシュとの録音を運良くLPレコードで見つけました。拍手の入ったライヴ録音です。PERENNIAL RECORDS Per.2007A & Per.2007B(レコードNo.SJS-703)。 ピアーズとのCDと比べてみるとルイスとのLPは驚くほどテンポがゆっくりしています。ピアーズ盤はせかされるように感じますが、ルイス盤はゆったりとしています。 ブラームスのホルントリオも一緒に入っていますが、こちらはBBCの復刻CDと同じ録音のようです。LPのブラームスにはハム(ノイズ)が入っています。
| |
504.ブレインのリヒャルト・シュトラウス | |
| name: | goshikinuma - 2003年06月24日 20時31分22秒 |
このシュトラウスのLPはイギリス盤です。ジャケットにはブレインの写真、マークにはあの犬のマーク(his masters voice)があります。番号はHLS7001です。このレコードはヒンデミットはオリジナル・ステレオですが、シュトラウスの2曲は当時はやりの擬似ステレオになっています。 このシュトラウスはあまり良い音ではないとずっと思っていましたが、今久々に聞きなおしてみますと、決して気にするほど悪いものではありませんでした。歯切れの良いブレインの名調子が聞こえてきました。聴いているとほんと楽しくなってきます。ひとつゴミがついていましたが、それは掃除して解決しました。これは当分ホルンのLPを聴くことになりそうです。その中にペーター・ダムが伴奏した「流れの上で」があります。シュライヤーのテナーがきれいです。してみると、ハウプトマンが伴奏したローテンベルガー(S)の流れの上でも欲しかったです。 | |
503.アファナシエフのシェック | |
| name: | goshikinuma - 2003年06月24日 20時12分05秒 |
アファナシエフはモスクワ放送のホルン奏者と思いましたが、ハイドンの録音が確かあったように記憶しています。 シェックの協奏曲はロジェストヴェンスキー指揮モスクワ放送響室内アンサンブルの伴奏で録音していました。ソビエト盤 33CM04283−84(a) アファナシエフの音はソビエト時代のホルンに共通の明るく、そして軽くヴィブラートをかけた演奏です。演奏そのものはブレインやバウマンにかないませんが、ソ連時代のメロディ録音の珍しさもあって購入していました。ちなみにLPのカップリングはモーツァルト、ベルリーニ、ウェーベルン、アイヴズ、ロガルスキーの管弦楽小品集でした。ホルンの曲はシェックだけです。 | |
502.ブレインのセレナード | |
| name: | goshikinuma - 2003年06月24日 16時59分00秒 |
いよいよ今日、久々にブレインのセレナードに針を通しました。私のLPはECS−507ですので、クリスマス・キャロルの祭典と小ミサ曲のカップリングです。本来ならECMの同じくピアーズのテナーのイルミナシオンとのカップリングで欲しいものです。 ブレインのLPはもう20年は聴いてないと思います。もったいなくてかけられません。保存が良いのでスクラッチ・ノイズは2回ほどしか入りませんでした。それにしてもこの演奏は絶品です。ピアーズもブレインも全盛期でした。ホルンのふくよかで温かくやわらかい響きは、どの演奏よりも良いと思います。これは数少ないブレインのffrr(デッカのモノラル名録音)のせいもあるでしょう。いや、デッカの名録音だったので生き生きした音が聴けるのだと思います。MDに落としましたのであとは聴き放題にできます。こうなるとCDを聴いてる暇がありません。カビがはえないうちに他のLPも聴かなくては・・・・ | |
501.ロシアのホルン・ヴィブラート | |
| name: | goshikinuma - 2003年06月24日 13時39分39秒 |
モスクワ放送響のホルンで私が引き合いにだされましたので・・・・・ ロジェストヴェンスキーのチャイコ全集ですが、70年代前半の72〜74年録音で、新世界レコードのレーベルだったころの全集です。音は良くありません。しかし別売のマンフレッドは音質が良い名演奏でした。 このころのホルンはそれほど極端なヴィブラートはかけていませんので違和感はありません。たしかに若いときイギリスのホルン奏者(ブレイン、タックウェル、シヴィル)で親しんだ耳にはヤコフ・シャピロの音はホルンじゃないとさえ思いました。初めてきいたのはロストロのドヴォルザークでハイキン指揮のモノラルでした。1楽章のホルンソロでなぜアルト・サックスの音が聞こえるのかと思ったら、やはりホルンでした。明るくて極端なヴィブラートは違和感ありました。 同じころフランスのヴェスコーヴォやバルボトゥの音を聞きましたらそっくりの音が聞こえました。これは帝政ロシア時代にフランスのホルン奏法を採り入れた当時のホルン奏法が残っていたということでしょう。 アレクサンドル・ガウクはチャイコの「四季」をオーケストレーションしていますが、LPは悲愴を持っています。もうひとつヤコフ・シャピロ他のホルンでシューマンの4つのホルンの演奏もモノラルLPで持っています。残念ながらコーガンとシャピロの共演のブラームスのトリオは入手できませんでした。しかしゴロワノフのCDの中にR・シュトラウスの協奏曲1番があって驚きました。かなりどろどろした演奏のように思いました。ブヤノフスキーの方がきれいです。 ブヤノフスキーはムラヴィンの60年録音のチャイ4で圧倒的な音を聴かせてくれましたので、コンチェルトのレコードをさがしましたらメロディア(輸入盤)にモーツァルト全集がありました。ハイドンも録音していましたがこれは独盤で入手できませんでした。やがて日本盤でソナタ集(ベートーヴェン、ロッシーニ、シューマン)が出ましたので、レニングラードのホルンのレコードと共に貴重なコレクションになっています。 ソビエト国立のホルンは68年に生演奏のチャイ5を聴いてすごいと思いましたが、もっと凄かったのは巨体のトランペット奏者です。真っ赤な顔でフォルテシモを吹くとホールが音の洪水となりました。あの馬力は凄かったです。ちなみにその時のプログラムはオール・チャイコフスキーで「ロメジュリ」トレチャコフのソロでヴァイオリン協奏曲、最後が交響曲第5番という金管泣かせのプロでした。 ソビエト国立のホルンは明るく伸びやかで深い響きが魅力的でした。 | |
