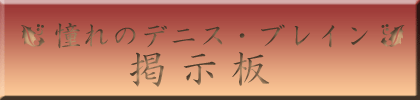
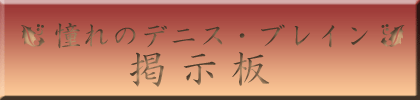
260.(欠番) |
259.バッハはむずかしい | |
| name: | Favart - 2002年11月27日 22時57分15秒 |
CATOさんはバボラークをかなり気に入っていると思っていました。私の話に合わせずとも、好きは好きで何ら差し支えません。人それぞれと思います。(音楽ファンの中には自分の意見こそが正しくて、自分と違う聴き方をしている人に対して「貴方は間違っている。」と言いたげな人も実際にいて、驚いたことがありますが。) バッハの音楽は音楽ファンにとっては本当に素晴らしく魅力的な音楽と思います。けれども、演奏者(特にプロの音楽家)にとっては恐ろしい音楽と思います。その演奏家の実力(音楽の核心部分)が丸裸にされてしまうようなむずかしさを持っていると思います。プロであっても生半可な取り組みをすれば見るも無残な結果となってしまい、そんな演奏も結構たくさんあるような気がします。つまり、「ごまかし」や「はったり」が全くきかない音楽と思います。バボラークについてはほんの少ししか聴いていませんが、私の「感」では、バボラークの場合、バッハの音楽が彼の中でまだ十分に熟成していないような気がします。「淡々とした」演奏でも中身が音楽的に充実した演奏もありますし、逆に「淡々としていない」演奏でも醜悪なものもあって、なかなかむずかしいものです。 私の好きなバッハ奏者の1人にエディト・ピヒト・アクセンフェルトがいます。淡々とした中でバッハの音楽に対して深い愛情が感じられ、聴くたびに、「ああ、すばらしい。」と感激してしまいます。残念ながら、少し前に亡くなってしまいました。 | |
258.「ブレインは自然の風の流れのような音楽」 | |
| name: | CATO - 2002年11月27日 22時22分22秒 |
だいきさん。 いい表現ですね。ホルンで議論が始まると常に陽性対照として参照せざるを得ないブレインが「自然の風の流れのような音楽」をやる人であった。何か凡人群と孤高の天才の対比の本質的な部分を突く様なことに思えます。 ついでに低音についてもう少し。ヒンデミットはブレインにあの名曲を捧げ、録音の指揮もして、かけがいの無い財産として残してくれました。低音の話題が出たので、低音(というかブレインしか出せないような、少し人によっては品が無いと難癖をつけそうなバリッと強い低音)に注目して聴いてみました。とはいえ、いつもながらの仕事の傍らですが。その結果、ヒンデミットはブレインのあのバリ低音を評価していなかったのではと思いました。この曲には区切り区切りにあの低音を強調する箇所がありません。低音の魅力は重要と考えられていないようです。ブレイン本人はあのバリ低音に自身を持っていたはずですし、事実ファンには堪えられないミエ切リの箇所です。「ヒンデミット先生、曲の献呈に感謝します。・・・しかしなんか忘れちゃーいませんか・・」と森の石松の気分ではなかったか。この曲に関しては、クレンペラーが遅すぎるテンポを設定してブレインと衝突したエピソードが「奇跡のホルン」に紹介されています。ひょっとして、これはブレインのよさを最大限活かせるテンポであったのかも、とも想像しました。 | |
257.私のクリスマス・アルバム | |
| name: | 夢中人 - 2002年11月27日 22時02分17秒 |
エリザベート・シュワルツコップのクリスマス・アルバム(CDM 7 63574 2、P1990)。ミーハー的内容と思いきや結構しっかり楽しめました。共演は、チャールズ・マッケラス指揮フィルハーモニア管弦楽団、アンブロジアン・コーラスとオルガンのデニス・ヴォーハン、ギターのジュリアン・ブリーム。録音は1957年の5月から6月にかけて。 「聖しこの夜」はオーストリアのオルガン奏者で校長先生だった、フランツ・クサヴァー・グルーバーのオリジナルの譜面が使われており、ギター伴奏とデニス・ブレインのソフトでヨーデルを思わせるようなソロがとてもオリジナルの鄙びた味わいを伝えます。またブラームスの子守歌「眠りの精」では魅惑的なホルン五度のハーモニーを聴くことができます。 最後の「イースター・アレルヤ」はMr.ビーンの映画でも教会で歌われていたもので、その場面が思い出されました。最近イギリスの教会では、若い人たちがあまり賛美歌を歌わない、と聞きますが実際はどうでしょうか。 LPはモノラルでしたが、CDは同時に実験的にステレオ録音されたマスターを使用しています。最後にもう一度「聖しこの夜」のモノラル・バージョンがおまけに収録されていて、今度はシュワルツコップが二重唱(二重録音)で歌います。ともかく凝ったアルバムです。 | |
256.無伴奏について | |
| name: | だいき - 2002年11月27日 17時55分28秒 |
バボの無伴奏は確かに淡々と処理している部分がありますが、ホルンという楽器の特性を考えれば淡々とやっているところはかなりのテクニックがないと駄目だと思います。世界には他にも素晴らしい奏者がたくさんいて、バボ勝るとも劣らないテクニックの持ち主はいると思いますが、バボのように淡々と聴かすことは難しいと思います。ここらへんは人好き好きでしょうが、バボもブレインの淡々とした演奏を意識しているのではないのでしょうか。ブレインの演奏は今淡々としたと書きましたが私の印象ではブレインは自然の風の流れのような音楽と思っております。 これが人によっては淡々とやっているように聴こえる人もいるかと思いますが、 バボはブレインの自然の流れを意識してやっているような気がします。 これが人によっては淡々と聴こえるのだと思います。 テクニックがずば抜けているため非常に簡単に演奏しているように聴こえますが、 非常に難しいことをやっているのだなーという感想です。 まあ、ブレインとバボを比べるのも全然方向性が違いますし、一概に比べるのも 無理がありますが・・。 けど、私の中ではブレインがやっぱり1番好きですね。 自然の風がふくような音楽、そして掲示板で出てきました。ブレインの低音ですが、ブレインの低音の出し方はやっぱり天性だと思います。 ああいう自然の音楽性や音の出し方なんかを聴くと、 やっぱり死後、50年近くたっても人気があると思いますね。 | |
255.蛇足 | |
| name: | CATO - 2002年11月26日 23時26分16秒 |
Favartさん 私は「236」で、バボラークの演奏について「・・・淡々と処理しすぎ・・・」と書いており、音楽としては「私にはちょっと・・・」です。(どうでもいい但し書きですみません) | |
254.残念ながら・・・ | |
| name: | Favart - 2002年11月26日 23時00分19秒 |
CATOさん レコード芸術2002年12月号 の付録を聴いてみましたが、「私にはちょっと・・・」でした。バッハの音楽はすべてを包み込む偉大さを持っていると思います。バッハの指定した楽器でなくても、音楽が生きてくる。私はジャック・ルーシェのバッハもスィングル・シンガースのバッハも大好きです。けれども、無伴奏チェロ組曲のバボラークの演奏にはどうもついていけません。ここらへんのところは本当に個人的な嗜好の違いと思いますが。グレン・グールドのバッハも「私にはちょっと・・・」なのですが、それと同じようなことと思います。 | |
253.「251」(私はまだ聴いていませんが)。 | |
| name: | CATO - 2002年11月26日 9時28分55秒 |
Favartさん レコード芸術2002年12月号 の付録CDのトラック33でさわりが聴けます。 | |
252.ハーリ・ヤーノシュの《歌》 | |
| name: | 夢中人 - 2002年11月26日 0時15分00秒 |
もう30年程前になりますが、NHK交響楽団のコダーイ/組曲「ハーリ・ヤーノシュ」の《歌》で宮田四郎さんが吹かれたソロは圧倒的でした。 曲は組曲の3番目、賑やかな《ウィーンの音楽時計》の次、一転してジプシー風のヴィオラのソロで始まる情熱的な恋歌で、ホルンのソロは弦楽器の力強い伴奏に乗って、中低音ばかりで吹き鳴らされます。宮田さんのソロは音が低くなるにつれ、メリメリッ、バリバリッと鳴って、一体ホルンの低音がこんなに鳴るものか、と度肝を抜かされました。 その演奏に前後するように、本場、ハンガリー国立交響楽団が来日。ヤーノシュ・フェレンチークの指揮で同じ曲をやりましたが、もこもことした吹き方で大いに不満を覚えました。また名盤とされているイシュトヴァン・ケルテス指揮ロンドン交響楽団(多分バリー・タックウェル)やジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団(多分マイロン・ブルーム)のレコードを聴いても、宮田さんのソロを聴いた時の感動を超えることはありませんでした。 じゃデニス・ブレインはどうなんだ、という訳でそのレコード(N響指揮者でもあったウィルヘルム・シュヒター指揮フィルハーモニア管弦楽団、1952年12月31日・1953年1月1日録音、Parlophone PMC 1017)を「再発希望」に載せ続けています。 | |
251.豊かな低音、ソフトな高音、そして音色の均一性 | |
| name: | Favart - 2002年11月24日 23時59分27秒 |
|
といったところがフルートを演奏していても難しいところです。フルートの場合は約3オクターブの音が出ますが、音の高低がめまぐるしく変化することが多く、低い音から高い音へ、高い音から低い音へ滑らかに移らねばなりません。特に無伴奏の曲はここらへんが特に重要です。CATOさんのお気に入りのバボラークのバッハの無伴奏組曲も奏者に要求される技巧は並大抵のものでないと思います(私はまだ聴いていませんが)。バッハの無伴奏の場合、低音の上に曲が成り立っているのでしっかりした低音がでないことには演奏自体成り立たないでしょう。 バッハの無伴奏チェロ組曲はフランス・ブリュッヘン(リコーダー)、オーレル・ニコレ(FlでBWV1007とBWV1010)の録音があったと思いますが、これをホルンで演奏するのは、リコーダーやフルート以上に過酷なのではと思います。 バッハの無伴奏チェロ組曲(全6曲)は本当にすばらしい曲です。無人島にCDを1枚だけ持って行けるとしたら、私はたぶんバッハの無伴奏チェロ組曲のCDを持って行くでしょう。ちなみにチェロはヤーノシュ・シュタルケルです。 | |
