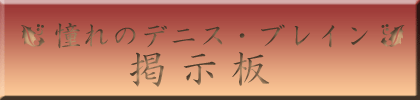
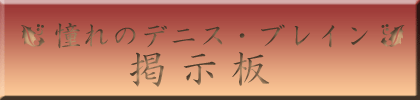
90.『英国音楽入門』から | |
| name: | 夢中人 - 2002年08月15日 9時16分51秒 |
>ブレインが新ウイーン楽派等の無調もしくはセリーの曲を担当している録音はあるんでしょうか? 7月25日のCATO様のご質問に「録音はない」と回答しましたが半分訂正して「録音はないようですが作品はあります」とさせて下さい! 作品とはペティット、山田淳さん訳の伝記に付録された初演リスト20頁にあるハンフリー・サール(1915-1982)の「ホルンと弦楽のための暁の歌 Aubade」で、昨日山尾敦史さんの「英国音楽入門」を読み直していてサールについての「ウェーベルンに師事した、英国では珍しい12音技法の使い手。ただしあくまで英国の作曲家らしい伝統色が見え隠れする・・・」とい記述に気がつきました。 この曲は初演リストにありますように1955年6月13日、オールドバラ音楽祭でデニス・ブレインとワルター・ゲーアの指揮、オールドバラ音楽祭オーケストラで初演されました。BBC第3放送が実況しましたが、ディスコグラフィーには記載がありませんのでどうも初演の録音は残っていないようです。作品はもちろんデニス・ブレインのために委嘱されたものですが、ちょうどサールが同時期(1955年7月)にチェルトナム音楽祭にむけて、友人のゴードン・ワトソンのためにピアノ協奏曲を頼まれていたためいずれもリハーサルに間に合わせるのがどうしようもなく大変だった、ということを自身で語っています。 作曲家曰く、この協奏曲 Aubade は、初期の作品と違って(新)ウィーン楽派の影響をあまり受けておらずやや外向的なスタイルを取っている。言い換えると、主にバルトークに影響を受けており、曲は打楽器だけで始まってスケルツォとフィナーレの間にはピアノと打楽器による間奏があり、全体として明るくて楽しいものになっている・・・。 他の作品には第1回ホフナング音楽祭(1956年)にはワルター・スコットの詩による語り手と打楽器のための「ロッキンヴァー」や代表作として10個の楽器のための変奏曲とフィナーレ作品34、その中にデニス・ブレインに捧げるホルンの楽章がある、といいます。 また夢中人は明日より100年ぶりの大雨と洪水に見舞われるヨーロッパへSPレコード返却の旅に向かいます。荷物が荷物のため以前東京の畳屋さんがされたようにパソコンを持参して同時中継するような芸当は望むべくもありませんが、元気で戻ってから結果報告するつもりです。 | |
89.ご存知王室御用達 | |
| name: | 夢中人 - 2002年08月13日 21時12分11秒 |
マルコム・アーノルドを取り上げてウィリアム・ウォルトン(1902-1983)を上げないのは片手落ちと思いました。夢中人のウォルトン初体験は、昭和54年の母校クラブの演奏会での戴冠式行進曲「王冠」、いわゆるクラウン・インペリアルです。いつも可愛い後輩達が懸命に演奏する姿を見るだけで感動してしまいますが、その時は曲の発するエネルギーにすっかり圧倒されました。 EMIが出した4枚組の全集(CHS 5 65003 2、P1994) The Walton Edition は、これにヤッシャ・ハイフェッツの弾くヴァイオリン協奏曲(BMG、7966-2-RG、P1988)やウィリアム・プリムローズの弾くヴィオラ協奏曲(EMI、CDH 763828 2、P1991)を加えると、作曲家自作自演による、それもほとんどデニス・ブレインのいるフィルハーモニア管弦楽団の演奏で揃います。 「王冠」は1937年、先の国王ジョージ6世の即位の際にBBCの委嘱により作曲されましたが、1953年のエリザベス2世女王の戴冠式行進曲「王の宝玉と杖」もウォルトンが作曲しました。今度はイギリス政府の委嘱ですから、もう完璧王室御用達という訳です。 この戴冠式の様子は、ペティット(山田淳さん訳)の伝記に詳しくありますように、イギリス中のトップ奏者を集めた特設オーケストラをエードリアン・ボールトが指揮して式典に華を添えました。BBCが実況したものをEMIがLP化。それを1997年にバジェット価格でCD化(CDZB 5 66582 2)しましたが日本の店頭に並びませんでした。 実を言いますと夢中人のお気に入りは20年以上たった今もクラウン・インペリアルのまんま。あまり進歩がないので山尾敦史さんの「近代・現代英国音楽入門」(音楽之友社、1999年)を読んで「ファサード」やオペラ「トロイラスとクレシッダ」の重要なことは承知しているつもりなのですが、こんなんじゃダメですね。 | |
88.ブリティッシュ・クラシックスへ送る新しい風 | |
| name: | 夢中人 - 2002年08月13日 13時40分06秒 |
1956年ホフナング音楽祭に出演したデニス・ブレインがオルガンを弾いたのがマルコム・アーノルドの「大々的序曲」。3台の電気掃除機と1台の床磨き機の演奏者にはアーノルドや指揮をしたノーマン・デル・マーのご夫人方があたりました。アーノルドはデニス・ブレインと同い年(1921年)でもともとロンドン・フィルハーモニー管弦楽団のトランペット奏者(1942-44、1946-48)。写真で見るとかなり大きな体格の持ち主ですので、さぞラッパの腕前も確かだったのではと思わせますが、入団7年で辞めて作曲に専念しました。 アーノルドが他の小難しい作曲家と違うのは、常に演奏家や聴衆の目線から曲を書いたこと。ド派手ながら時には心に沁みる、判りやすくて格好の良い音楽でもって伝統と格式を重んじるイギリス音楽界に殴り込みをかけました。よくイギリスのオーケストラは中庸とか堅実といった言葉で表現されて、そんな真面目さが実は好きだったりしますが、そんな本質と正反対に時として羽目ををはずして暴れ回ることを最初にやらせたのが彼だったといえないでしょうか。 デニス・ブレインのいたフィルハーモニア管弦楽団との録音は、バレエ曲「女王への忠誠」、「イギリス舞曲集」(1953.6.11&12録音)「スコットランド舞曲集」(1957.1.16)(EMI CDM 5 66120 2、P1996)、「イギリス舞曲集」の第3番と第5番は同じプロデューサー(Alan Melville)による別録音(1955.9.19、EMI CDM 7 64044 2、P1991)がある位ですから余程のお気に入りだった様子。指揮は前者がロバート・アーヴィング、後者が作曲家本人です。 | |
87.いつもながらの | |
| name: | Favart - 2002年08月11日 21時44分52秒 |
夢中人様の豊富な情報と解説!本当にありがとうございます。K.487の使用楽器はケッヘル氏はヴァイオリン、旧全集ではバセットホルン、そして新全集(D.ベルケ)でナチュラル・ホルンとの結論に到達したとのことです。フルニエの全曲録音、是非聴いてみたいですね。手持ちの資料(小学館)では「クルニエ、ガンティス(78CP)」とあり、これはフルニエの間違えのようですが、1978年Counter Point(米)のレコードがあるようです。 先日、夢中人様にうかがった「Robert L Mershall : DENNIS BRAIN ON RECORD」の件、OSMUN MUSICに問い合わせたところ、「I'm sorry. We no longer carry this book.」とのことでした。残念! 私の方はしばらく夏休みに入ります。夢中人様も良い夏休みをお過ごしください。 | |
86.モーツァルトとロイトゲープ | |
| name: | Favart - 2002年08月10日 19時06分29秒 |
ロイトゲープ[Ignaz Leutgep c.1745〜1811]がなぜザルツブルクからヴィーンに移り住んだかは分りませんが、1777年までザルツブルク宮廷楽団員を務めた後、モーツァルトより一足早くヴィーンに移り、チーズ商を営みながらホルン奏者として活躍したそうです。 モーツァルトが初めてロイトゲープのために作曲した曲はホルン五重奏曲(K.407、おそらく1782年の終わり、ヴィーン)だそうです。ホルン五重奏曲は協奏曲第1番に続いて書かれたと推定されていましたが、協奏曲第1番の成立年が1791に訂正されたため、この曲がロイトゲープのための第1作となりました。モーツァルトのホルンの曲はこの他に「ホルンのための12の二重奏曲(K.487、1786年7月27日、ヴィーン)があります。第1曲の自筆譜には「1786年7月27日ヴィーンにて。九柱戯をしながら」と上書きされているとのこと。自筆譜には楽器の指定がなく、長い間使用楽器を巡って研究家を悩ましてきたそうです。使用楽器が当時のナチュラル・ホルンとすると、ほとんど不可能な音域(記譜でg3)が4曲にあり不可解なものとなるそうです。ところが、このことに謎を解く鍵が隠されていたとのことで、モーツァルトが九柱戯(ボウリング)仲間のロイトゲープと遊びに興じていた時、たまたまホルンの技巧が話題となり、モーツァルトは即座にこれらの小品を書き、いつものようにロイトゲープをからかったとのことです。 ロイトゲープはホルン協奏曲第1番のジュースマイヤーの補筆が完成した年の1792年にホルンの演奏をやめ、以降チーズ屋に専念し、1811年ヴィーンで没した時の借金が1286グルデンであったとのこと。モーツァルトと同様にザルツブルクの宮廷楽士の職を離れたことが、貧乏の元になったのでしょうか。でも、できたてのモーツァルトの曲を演奏できたロイトゲープはなんと幸せな男だったことでしょう! ・海老沢敏氏他監修「モーツァルト事典」(1991.11.7東京書籍) ・石井宏「帝王から音楽マフィアまで」(1993.2.15新潮社)〜「モーツァルト、その知られざる遺言」
| |
85.レオポルド・モーツァルトの場合 | |
| name: | 夢中人 - 2002年08月10日 9時31分45秒 |
NAXOSの今月の新譜(Marco Poloからの移行、8.555978)にアルペンホルンのための協奏曲集が出ましたので早速入手しました。お目当てはレオポルド(父)・モーツァルト(1719-1787)のアルペンホルンと弦楽のための田園風シンフォニアです。手持ちのBielefelder Katalogには5種類も載っていて、何時かは聴いてみたいと思っていました。 父モーツァルトは、昔ヨゼフ・ハイドンの曲とされた「おもちゃの交響曲」で有名ですが2本のホルンのための協奏曲や狩りの交響曲などホルンのための曲を好んで書きました。これは夢中人の想像ですが、父モーツァルトはこれらの曲を書いてザルツブルグ大司教宮廷楽団のイグナツ・ロイトゲプを含むホルン奏者に吹かせた。ロイトゲプはロイトゲプで受け狙いのような曲ばかりをやらされるザルツブルグが嫌になって、息子アマデウスを追うようにウィーンへ行った・・・。 1956年11月13日、第1回「ホフナング音楽祭」。デニス・ブレインは、この父モーツァルトの曲(第3楽章のみ)をラッパがわりの漏斗(じょうご)を付けずに、本当に何メートル巻いただけのゴムホースで演奏しました。音楽祭はその年の4月に企画されたと言いますから、独奏者のデニス・ブレインと指揮者のノーマン・デル・マーは、ロイヤル・フェスティバル・ホール(RFH)の観客をアッと言わせるため周到な用意をしたに違いありません。ペティットの伝記に舞台写真が載っていてよく現場の雰囲気を伝えます。 この時の実況録音は、大至急EMIがレコード(33CX1406)にしてその年のクリスマスに出してからずっとカタログにあります(CMS 7 63302 2、P1989)。またデニス・ブレイン以来何人もゴムホース吹きが現れました。1988年にはフィルハーモニア管弦楽団が同じRFHで催した同音楽祭(この時はリチャード・ワトキンス)をDECCAがCD化しています。
| |
84.夢中人様 | |
| name: | 大山幸彦 - 2002年08月08日 13時24分07秒 |
おそくなりましたが、LPOの件ありがとうございました。 ショルティの件面白かったです。かれはたぶんホルンに対してかなりの 規制をする人だと思います。先生ともよく喧嘩したらしいので。 | |
83.モーツァルトのホルン協奏曲-補遺 | |
| name: | Favart - 2002年08月07日 0時05分52秒 |
夢中人様、コメントをありがとうございました。勉強になりました。オーブリーがK.371の楽譜をデニスでなくアラン・シヴィルに渡した件はデニス・ブレインの映画ができそうですね。「モーツァルトとサリエリ」でなく「オーブリーとデニス」。題して「悲劇の天才ホルン奏者デニス・ブレイン〜イギリス名門音楽一族の父と子の葛藤!」ただ、DBはまじめすぎるから客足は「アマデウス」にはニ歩〜三歩及ばないでしょう。 海老沢敏氏他監修の「モーツァルト辞典」(1991.11.7東京書籍)では次のようになっていました。ご参考まで。 K6.370b(断片) 1781年、ヴィーン K.371(断片) 1781年3月21日、ヴィーン K.417 1783年5月27日、ヴィーン K6.494a(断片) 1785年中頃〜末、あるいはそれ以降、ヴィーン K.495 1786年6月26日 K.447 おそらく1787年、ヴィーン K.412/514(386b) おそらく1791年1月から10月の間、 終楽章の完成稿は1792年4月6日、 ジュースマイヤーによる?、ヴィーン *1791年12月5日午前零時55分モーツァルト没。 掲示板の過去ログを見ていたら、「ロ短調ミサ曲」のことも「ケンペorケンペン」のことも書いてあったのですね。ケンペの愛好家の書いた本を読んでみたいですね。 | |
82.モーツァルトのホルン協奏曲についてもう少し | |
| name: | 夢中人 - 2002年08月06日 19時22分34秒 |
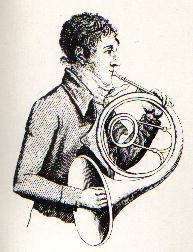 Favart様の「80.モーツァルトのホルン協奏曲」を読んで以来何度も考えます。もし、デニス・ブレインが1番が1番最後の作品だったことを知り得ていたら、と。 Favart様の「80.モーツァルトのホルン協奏曲」を読んで以来何度も考えます。もし、デニス・ブレインが1番が1番最後の作品だったことを知り得ていたら、と。COLOMBIAの全曲LP(33CX1140)でMcKay Martinは、ふたつの楽章しかない第1番のアンダンテ楽章と考えられる未完の断章の楽譜をある学者(アインシュタイン)が持っていること。第1楽章で出てくるバズーンが第2楽章では無い(のはおかしい)こと。また3番は4番より短いけれども音楽的には優れているとも解説。とても暗示的な内容でした。 その未完の断章ホ長調は、デニス・ブレインがBBCラジオ3の番組「初期のホルン」で初演(1955.7.6録音、同7.23放送)した後、1957年6月のオールドバラ音楽祭でも演奏しました。当時K.Anh98a(のちにK.494a)という作品番号が付いたこの演奏録音テープをBBCは消してしまったと言いますから返す返すも罪な話ですね。 断片的な独奏曲は他にもあります。ホルンのためのコンサート・ロンド変ホ長調、K.371で戦前オーブリー・ブレインはその楽譜を息子のデニスではなく、アラン・シヴィルに渡しました。おかげでデニスは「吹いたことがない」と言いましたから可哀想。(ケンペ/RPOとの2回目の全曲録音でこのロンドを録音) もうひとつ。皮肉なことに現代のホルンで吹いて一番聴き栄えがするのが、断章K.370b。 モーツァルトが最初にロイトゲプの為に書いた曲で、ロイトゲプが「難しくて吹けない」とダメ出しました。実はこれがコンサート・ロンド、K.371とペアでオランダのヘルマン・ユウリセンがホルン協奏曲「第5番」、K.494aを同「第6番」として1980年に録音しました。これには現代のホルン吹きだけでなく、天国のデニス・ブレインも目を丸くしたことと思いますが、この時点でも1番はやはり1番。びっくりがこれで終わらなかったことは、Favart様ご紹介のとおりです。 1994年にEMIが出した執念のリマスター盤では第1番ニ長調、K412/(6)386b(K514バージョン、ジュスマイヤー編曲)とクレジットされましたが、さすがにこれには長々とした説明(ちょうどこの投稿のように)が必要で、曲順も2→4→3→1にはなりませんでした。それでも1番は1番という訳です。 まさに思考錯誤の歴史。そういった意味でトンプソンのCDは決定盤たりえるのでしょうか。最後にその収録順を書いて終ります。 断章変ホ長調 K.370b ロンドー変ホ長調 K.371 協奏曲第2番 K.417(1783年) 断章ホ長調 K.494a(1785〜1786年) 協奏曲第4番変ホ長調 K.495(1786年) 協奏曲第3番変ホ長調 K.447(1787年) 協奏曲第1番ニ長調 K.412(1791年) アレグロ・ロンド ロンドニ長調 K.514(1792年4月6日、フランツ・クサヴァー・ジュスマイヤー完成版) | |
81.「奇跡のホルン」読んでます | |
| name: | CATO - 2002年08月04日 9時18分26秒 |
春秋社から届いた本は1999年の第二刷でした。 読み終えるのもったいないような本で、今はバラバラに虫食い読み中です。なお、教えてもらったように、英語版は今入手できないと、これまたAmazonからメールが入りました。こんなに興味深い本こそ英語日本語ともに繰り返して読んで、少しばかりは英語の力を付けたいものを。 ブレインが9歳の時に扁桃腺手術のミスで嗅覚神経を破壊され、その後事実上味覚を失ったというくだりで胸がいたくなりました。旨いものを楽しんで食って、もっと太って、無理なスケジュールを強気に断るようなペースで生きてほしかった。 | |
