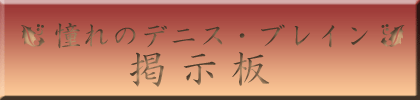
前へ | 過去ログメニューへ|次へ
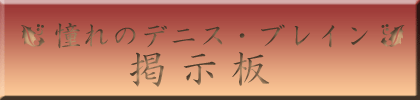
760.DUTTONのCD復刻 | |
| name: | Favart - 2004年04月24日 22時32分35秒 |
少し前に夢中人様に教えていただいたDUTTONのMoyseのCDを聞くことが出来ました。Moyseの全盛期の録音はすべてSP録音でノイズや狭い周波数レンジで隔靴掻痒の感がありますが、このDUTTONの復刻CDはすばらしい出来栄えです。ノイズがほとんどなく周波数レンジが広く、そして最も肝心なフルートの音が自然でMoyseを目の前で聞いているような錯覚を覚えます(特にバッハのトリオ・ソナタ)。SPのCD復刻はレコーディング・エンジニアのセンスにより大きく成否が分かれますが、このDUTTONの復刻はほれぼれします。ほかのSPのCD復刻もすべてこの人物にお願いしたい気になります。DUTTONのブレイン/グリラー四重奏団のモーツァルトもとてもよかったと思います。次はR.シュトラウス/協奏曲No.1(ガリエラ指揮PO)、モーツァルト/協奏曲第2番(ジュスキント指揮)、同/第4番(ハレ管)などのSPのCD復刻お願いしたい気になります。R.シュトラウス/協奏曲No.1のPearl盤CDのお粗末さ(音抜け)にはがっかりしました。 | |
759.思いつき | |
| name: | CATO - 2004年04月16日 21時37分28秒 |
TGIF,です。また毎度バカバカしいことを少し申します。 チャーリー・パーカー(1920-1955)=デニスブレイン(1921-1957)。 このサイトを見ている方の1/100は同感と思います。私はずっと書きたかったけど、どちらかの真のファンには軽すぎると誤解されそうなので書きませんでした。(軽い人間が慎重になっても仕方ないですが。) どちらも弾けた音の天才です。もう、これ以上することが不可能な天才の悩みを共有していたと思います。ブレインはパーカーを知っていたけど、逆は多分無かったと想像します。ブレインといえばT.ドーシーですが、パーカーを知らなかったとは思えません。私のパーカー推薦盤は今は書きません。何か反応があることは期待大ですが。 | |
758.補遺かな | |
| name: | CATO - 2004年04月10日 19時38分43秒 |
けど、まじめな補遺です。 クレンペラー/POの29番も愛聴盤です。あと29番ではLPでベーム/BPを持っています。皆好きです。特に大学生の頃はベームの、境地に達したような遅い1楽章の滑り出しに、名人を感じていました。このLPは28番とのカプリングで、これの3楽章のホルンの素朴な役割が今でも大好きです。28番にもしびれていた頃、大フィルで28番を聴き、生は生ですばらしいと認識しました。生で聴くとモーツアルトにおけるホルンの効果がよくわかりますね。 Favartさん、いつも粗い投稿の連鎖をまとめていただけて感謝しております。ご記載の、S=\3,000 というのが、泣かせますね。それと、東京文化会館といえば、大学一年の夏休みにホール見学に行って、N響の主席トロンボーンの伊藤さんと偶然10cmくらいまで接近して大感激であったのを思い出しました。 もう30年ほど前の話です。 | |
757.ダヴィッド・オイストラフ1967年日本公演(739補遺)他 | |
| name: | Favart - 2004年04月10日 17時35分10秒 |
部屋の整理をしていたらオイストラフ日本公演のチラシとチケットが出てきました。なつかしいので、ちょっと書かせてください。 1967年3月25日(土)7:00P.M. 東京文化会館(大ホール) 主催:毎日新聞社・新芸術家協会 S=\3,000 〜 D=1,000 ピアノ:フリーダ・バウエル(Frieda Bauer) シューベルト:ソナタ・イ長調 作品162 ベートーヴェン:ソナタ・イ長調・<クロイツェル> ドビュッシー:ソナタ・ト短調 ショスタコーヴィチ:三つの幻想的舞曲 タルティーニ:ソナタ・ト短調・<悪魔のトリル> シューベルトの他に「クロイツェル」や「悪魔のトリル」を聞いたこともおぼろげながら思い出しました。オイストラフはもちろんすばらしかったですが、バウエルのピアノは女性らしい温かみのある演奏でした。(ちなみに当時私は高校生!) オイストラフとブレインのPOとの録音はハチャトリアンの協奏曲(作曲者指揮、1954.11.27録音)の他にラロのスペイン交響曲(マルティノン指揮、1954.11.14録音)があるそうです。 CATOさん、BPOの管楽器奏者は本当にすばらしいですね。特に60年代は名手ぞろいで黄金時代だったと思います。ツェラーとコッホはブランディス(Vn)、ウェーベルシェール(Va)ベッチャー(Vc)、レヒナー(Cemb・・・小林道夫さんの先生)、デーリンク(Cemb)らとベルリン・フィルハーモニー・ゾリステンを結成して各地で演奏会を開いていました。このころの録音「大バッハの息子たち」は私のお気に入りです。ツェラーはこのBPOゾリステンの南米演奏旅行の際に大怪我をしてBPOから離れましたが、後に奇跡的に復帰。ツェラーの前任のニコレも少し前に交通事故でケガをしたそうです。 ザイフェルトの方はベルリン・フィルハーモニー八重奏団でディヴェルティメントK.334やホルン五重奏曲K.407を録音しています。エッシェンバッハ(Pf)とのブラームスのホルン・トリオOp.40もありますね。 goshikinumaさん、CATOさんヒンデミットのホルン協奏曲の感想を聞かせていただき、ありがとうございました。もうすこし聞き込むと私も好きになれるかもしれません。33CXはモノーラルですがステレオの必要性を感じないほど良い音です。ブレインのホルンも勿論すばらしい。 | |
756.755補遺 | |
| name: | CATO - 2004年04月10日 7時41分53秒 |
どうも最近粗い言い方が多いようで、失礼しています。 そこで、以下はネットの記載からですが、ライブのあった1964年あたりのBPの管を見てみました。というのも、「755」のCDでとろけるようなオーボエが印象深いからです。すごい奏者を集めたもんです。 1957年:オーボエのローター・コッホが首席就任 1959年:クラリネットのカール・ライスターが入団 1960年:フルートのカール・ハインツ・ツェラーが入団 1963年:(新ホール完成) 1964年:ゲルト・ザイフェルトが首席奏者に就任 | |
755.クレンペラー | |
| name: | CATO - 2004年04月09日 21時54分58秒 |
「753」と直結ではないですが、同じ標題で失礼します。 testamentのCDはシヴィル以来かなり私のお気に入りです。大阪梅田のタワーレコードに行っても、まずこのレーベルのチェックで60分です。変なおじさんさながらに行ったり来たりです。 最新の収穫は、クレンペラー/BPのバッハと田園とモーツアルト29番のライブです(SBT2 1217)。録音は決してよいとは言えません。けど、これを言っちゃおしまいですが、POとは合奏能力が違います。完璧な弦の塊と無双の管。録音1964年のBP。おそれいります。指揮者は、イメージの指示のみでよく、アタック弱い、不揃いだ、などのストレスはゼロです。 | |
754.ありがとうございます | |
| name: | goshikinuma - 2004年04月07日 13時12分10秒 |
夢中人さんありがとうございました。 なるほど翌日の演奏会を考えて欠席と考えればうなづけます。ただどうにも 3楽章の冒頭のホルンの強奏の後で消えるのが不可解でした。ひょっとすると 編集でつないだかと思うほどです。テンポの変化がありますので考えられます。 それはわかりませんが、いろいろの第5を聞いていますと、他の録音にも 不可解なものがいくつもあります。とにかく面白いです。 | |
753.クレンペラー | |
| name: | goshikinuma - 2004年04月06日 20時06分27秒 |
皆さんお久しぶりです。 ヒンデミットはR・シュトラウスとカップリングになっていてこの曲だけ オリジナルステレオ録音でしたから、大変好きでブレインの音にいつも酔い しれていました。逆にノイネッカーの台詞付きが違和感あるくらいです。 ヒンデミットといえば確かクレンペラーが指揮を断った経緯があったように 思いましたが、そのクレンペラーの1955年の第5を今日アップしました。 それが実に不可解で、第1、2楽章でブレインのホルンがよく響き、第3楽章の ホルンの強奏でもブレインがバンバン吹いていましたが、その後からブレインの 音がぷっつり消えています。しかもホルンのテーマのテンポとそのあとのテンポが 違います。遅くなっています。トラぶったのかなとしか思えないです。第4楽章の コーダのホルンの主題もあきらかにブレインの音ではありません。サンダースかも しれません。シヴィルは56年からの入団でした。 夢中人さんはこの録音の経緯はご存知ありませんでしょうか。
| |
752.同感です | |
| name: | CATO - 2004年04月06日 0時31分02秒 |
ヒンデミットの曲に対する私の意見は前に何回かここに書きました。 彼は音楽家というより理論の著書も多い音楽学者で、音楽を愛していたが、愛される音楽、特に旋律が書けなかったと思います。全般に鬱蒼としていて、暗いです。(また 言い過ぎた)。 とにかく作曲上手なので、例えばウエーバーから主題を持ってくると面白い聴きやすい音楽になっていますね。乗れる年代であったのに12音以降の流れには合流せず、行き詰まるのも必然だったのでは。ブリテンでさえ、あんなにブレインと近しくしていたのに、普通のホルン協奏曲は書か(け)なかった。 ブレインがもう20年も生きていれば、12音以降の作曲家に多くの曲を書かせたでしょう。たとえば、ベリオにはセクェンツァ(シークエンス)という種々の楽器用の面白い曲があり、私には例えば、トロンボーンのグロボカールが吹いた録音の重音奏法と即興性などが印象的でした。これを初めて聴いたとき、ブレインのことは知っていて残念な思いがしたのを思い出しました。 | |
751.ヒンデミット「ホルン協奏曲」 | |
| name: | Favart - 2004年04月03日 21時44分36秒 |
デニスがモーツァルトを演奏するのを耳にして大変に感動したヒンデミットがデニスのために作曲した曲だそうです。ようやく33CXの「1N」で聞くことができました。デニスの演奏はのびのびしていて難曲であることをいっさい感じさせません。柔らかくて、とても美しい音色。そして自由自在な演奏。でも正直なところ、この曲は私には重苦しいのです。R.シュトラウスの協奏曲(特に第1番)は大好きなのですが、ヒンデミットは聞くのがつらい。ヒンデミットの初心者ですので、繰り返して聞いているとよくなってくるかもしれません・・・。皆様はいかが? | |
