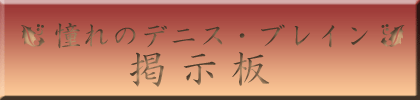
前へ | 過去ログメニューへ|次へ
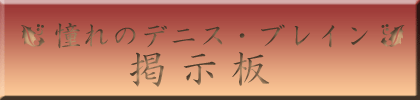
620.ミケランジェリの | |
| name: | CATO - 2003年11月01日 23時20分12秒 |
DVDとか、復刻とか、ファンには有難いですが、なんかもうこの世に居ないことの寂しさもひとしおです。ウ〜ン四時間も。こうなると、ディスク録画がしたくなります。持ってませんが。 それと夢中人さんのご意見。PC、ネットて何でしょう。結局うたかた?見散らかして、たまに刷ったものもろくに見なくて。本をめでるとか、音盤に息を吹きかけて、バーのマスターよろしく慈しんで磨くとか、なくなりましたね。これはおじ様族の繰言ではないと思います。有り難味を忘れて時間つぶししている時代ですね。 今日は東京日帰り仕事でした。前も言いましたが、渋谷タワーレコードめぐりをする体力が無い自分が情けなかったです。10年前はわくわくして見て買って、最終の新大阪着が平気でしたが。 Willis(かなり巧いです)のロセッティと、ブーレーズ/NYPの水上の音楽を最近同時に買い、聴いています。ホルンの音色というより独特な音色のオケに驚いています。ブーレーズが尖がっていた時のヘンデルです。また、そのうち聴き比べを書きたく思います。 | |
619.ラウーによるモーツァルトのディヴェルティメント | |
| name: | Favart - 2003年11月01日 20時35分41秒 |
たまたまラウーのナテュラル・ホルンによるLPレコードを見つけ聞いてみました。 ラウーのナチュラル・ホルンは1798年頃と1800年頃のもの、2本です。ホルンの音色は小ぶりでソフトで軽く、ちょうどいい具合に引き締まっていてモーツァルトのディヴェルティメントにぴったりの印象をもちました。ブレインでおなじみのK.270も全体のバランスがとれた演奏と思いました。このレコードはホルンだけでなく、他の楽器も1780年〜1810年頃のオリジナル楽器で第2ファゴットを除きすべてパリ製。古楽器の古めかしい印象は皆無です。心地よい響きです。 「木管とホルンのあいだの音響上のつりあいの問題は、現代の楽器では往々にして克服することは困難であるが、古楽器を用いることでほとんどなくなるように思われる。ナトゥーアホルンは今日の半音階ホルン(それはヴァーグナーの楽劇や“春の祭典”のごとき作品の要求には叶うはずであるが)よりもじっさい上「ずっとやせた」音をもっており、そのためオーボエやファゴットとの協演にはよりいっそう適しているものである。」(解説より:マリウス・フロトホイス、訳/海老澤 敏) 曲目は「2つのオーボエ、2つのホルン、2つのファゴットのためのディヴェルティメント、ヘ長調 K.213、変ホ長調 K.289(271g)、変ロ長調 K.270、ヘ長調 K.253」の4曲でフランス・フェスター指揮ダンツィ五重奏団の演奏。 第1ホルン:アドリアン・ファン・ウーテンベルク(ラウー、パリ、1798年頃) 第2ホルン:イマン・ゾーテマン(ラウー、パリ、1800年頃) 録音:1973年ウィーン (SEON原盤、日本ポリドール MLG 1011) *フランス・フェスターはもともとはフルート奏者。 CATOさん ミケランジェリの放送があります。 11/22(土)前0:00〜4:00 NHK-BS2 「アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ・ピアノ・リサイタル」 曲目は不明です。月刊「ぶらあぼ」11月号より。 | |
618.Beulahの愛 | |
| name: | 夢中人 - 2003年11月01日 13時19分15秒 |
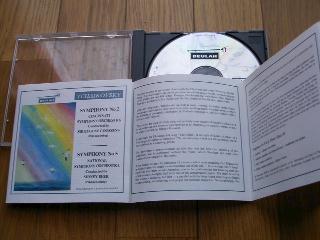 「詳しくはホームページで」と最近よく言いますが、じゃパソコン(PC)をやらない人はどうするの?みたいなことをいつも考えます。何と言っても現在のPCは操作が難しくテレビのようにボタンひとつで直ぐ見られるという代物ではないのでやはり面倒でも従来どおり「紙」でも閲覧できるようにするのが親切というものではないかなと思います。そのホームページで英国のBeulahレーベルが2001年からCDの生産を中止しているのを知り悲しくなりました。 「詳しくはホームページで」と最近よく言いますが、じゃパソコン(PC)をやらない人はどうするの?みたいなことをいつも考えます。何と言っても現在のPCは操作が難しくテレビのようにボタンひとつで直ぐ見られるという代物ではないのでやはり面倒でも従来どおり「紙」でも閲覧できるようにするのが親切というものではないかなと思います。そのホームページで英国のBeulahレーベルが2001年からCDの生産を中止しているのを知り悲しくなりました。数年前までは英国の独立系CDレーベルはデニス・ブレインに関係するレコードの復刻にとても熱心で、カタログ請求の際にリクエストを書いておくとしばらくすると本当に出してくれるような感じもあったんです。Beulahは早くからDeccaのSP録音を復刻していました。その後カタログが請求もしないのに毎年来ていました。 ペティット/山田さんの伝記で登場する「ナショナル交響楽団」の録音を最初に出したのもこのレーベルです。23歳のデニス・ブレインがソロを吹くチャイコフスキーの第5交響曲も出しました。それとこのレーベルのジャケットは美しい絵画が飾られていて他が大抵ホチキス止めであるのに対し、写真のように蛇腹(じゃばら)になっているのに特徴がありました。ホチキスは年が経つと錆びてくるのでCD一枚とはいえ製品に対する愛情がひしひしと感じられました。ちょっと時代遅れだけれどスタイルを持った英国製品が好きです。 Dutton Laboratoriesが同じくDecca録音を素晴らしくノイズ取りを行って出したものですからキャラが重なったBeulahはだんだん尻すぼみになってしまい上のようになったのかどうか。クラシックは近年特に売れないし。でも1999年秋に出たアンソニー・コリンズ指揮ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団のシベリウス名曲集(Popular Sibelius、BEULAH 5PD8)で「トゥオネラの白鳥」のコール・アングレを吹くのは兄レナード・ブレインで何と1957年9月録音です。ここにもBeulahの愛を感じます。 | |
617.Sarah Willis(BP第四ホルン) | |
| name: | CATO - 2003年10月31日 19時38分28秒 |
とWallendorfによる、ロセッティの2本のホルンのための協奏曲集(cpo 999 734-2)を今聴いています。レコード評を少しは見てから、私見をの述べます。こう御期待(誰もしないか)。演奏はさすが立派なものです。写真で見ると、Ms Willisはホルン向けの顎と歯並びをもつ美人です。
| |
616.訂正(578)---「ヴァチカンのミケランジェリ」 | |
| name: | Favart - 2003年10月29日 22時20分22秒 |
・・・やはり全くのうろ覚えでした。すみません。 <ヴァチカンのミケランジェリ> DISC-1 ドビュッシー 映像(第1集&第2集)、ラヴェル 夜のガスパール Nervi Hall,1987.6.13 DISC-2 ショパン アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Nervi Hall,1987.6.13 ドビュッシー 前奏曲集 第1巻 Nervi Hall,1977.4.29 DISC-3 ベートーヴェン 協奏曲「皇帝」 フレッチア/RAIローマRSO Hall of the Benediction, 1960.4.28 ベートーヴェン ソナタ第3番ハ長調Op2-3, Nervi Hall,1987.6.13 DISC-4 シューマン 協奏曲 リスト ピアノとオーケストラのための「死の舞踏」 ガヴァッツェーニ/RAIローマRSO Hall of the Benediction, 1962.4.28 発売元:日本コロムビア 999-001(4CD) (C & P 1995 FINWAY TRADING Ltd & APPASSIONATO AG ) CATOさん フルトヴェングラーの生まれた1886年にブラームスは53歳とのこと。意外でした。ブラームスはもっと昔の人のイメージがありました。わりと最近の人だったんですね。ミケランジェリは1920年生まれでD.ブレインより1歳4ヶ月歳上でした。ラヴェルの協奏曲の録音は1957年3月8日で、ミケランジェリ37歳、D.ブレイン35歳、グラチス41歳。みんな若かったですね。 | |
615.UK2003年11月新譜 | |
| name: | 夢中人 - 2003年10月29日 21時41分31秒 |
Sony Classical.UK よりサー・トーマス・ビーチャム/ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団新譜予定。 SMK91167 ベルリオーズ「イタリアのハロルド」(1951.11,13,15) グレトリー「ゼミールと犬」(1954.4.28) メユール序曲「ティモレオン」「にせの宝物」「若きアンリの狩」(1953.12) マスネ「聖処女の最後の眠り」(1953.12)←without Dennis Brain SMK91169 シューマン「マンフレッド」(1954.12 etc.)←without Dennis Brain SMK91171 ドヴォルザーク交響的変奏曲(1953.12) バラキレフ交響詩「タマーラ」(1954.4.16) リムスキーコルサコフ「金鶏」(1951.1.9,15,24) SMK93009 シベリウス「テンペスト」(1955)←without Dennis Brain アーネルバレエ組曲「パンチと子供」(1950.5.31,6.1) バーナー「ネプチューンの凱旋」(1952.2.3) Phiadelphia Orch.←without Dennis Brain
| |
614.映画「フルトヴェングラーと巨匠たち」 | |
| name: | CATO - 2003年10月28日 22時04分03秒 |
夢中人さんの、「611」へのコメントを見て、久しぶりにDVD(dreamlife DLVC-1038)を見返してみました。題名のとおり、フルトヴェングラーとBPが中心なので、例えばクナッパーツブッシュなどの映像が短すぎるなどの印象があります。フルトヴェングラーファンには堪らない映像集ではないでしょうか。印象的な場面は多々ありますが、戦後初のベルリン復帰コンサートの熱気が伝わる観客と舞台の映像は感動的です。また、出だしの独特な、ダンプカーが砂を吐き出すような、揃っていないようで揃っている音も、ワーグナーの映像ではよく感じられました。ホルンについての夢中人さんの観察の箇所もよく判りました。いかにものドイツ正統ホルン奏者という風貌でした。 調べたら、フルトヴェングラーは1886年生まれ。同じ年に山田耕作が生まれています。リストが75歳で没した年。マーラー、ブラームス、ブルックナーは存命中で、各々26歳、53歳、62歳です。判りやすいところで言えば、クレンペラーより一つ下で、きんさん・ぎんさんより6つ上です。 | |
613.KV 297b; KV Anh.C 14.01 | |
| name: | Favart - 2003年10月28日 0時05分56秒 |
の初録音が1940年、近衛秀麿/BPOとは!日本人としてこれは快挙!と言えます。 HIDEMAROがNIDEMAROになっているのはご愛嬌でした。 Oubradousの録音は1950年で10年後。こちらのホルンはたしかDevemyでしたね。 興味深いHPを教えていただき、ありがとうございました。 フルトヴェングラー/BPOの「魔弾の射手」をSPで持っていますが、ホルンがどんな音かもう一度聞いてみようと思います。1940年代の録音と思います。 | |
612.少し古いかもしれませんが | |
| name: | Favart - 2003年10月26日 21時55分11秒 |
|
1928年11月5日のフルトヴェングラー/BPOロンドン公演のホルン奏者は OSKAR SCHUMANN, LEONHARD TIERSCH, GUATAV OTTO, GEORG HEDLER, OTTO HESS,R UDI RANKとのことです。 OSKAR SCHUMANNはケルさんのコレクションにあったような・・・? 1928年のメンバー表で知っている奏者がいるか探してみたところ、なんとチェロの巨匠GREGOR PIATIGORSKY[1903.04.17-1976.08.06]がトップに入っていました。
| |
611.一部訂正(610) | |
| name: | Favart - 2003年10月26日 9時28分27秒 |
|
「トリミングなしと思われる・・・」と書きましたが、あらためて写真を見ると右端がトリミングされていました。P123の写真の方が少し広く写っています。P123の写真と特に違うところは上部が広く写っていて円形のマイクロフォン全体が写っていることです。このことで録音会場の雰囲気が感じられます。P123の写真だと半円形の物体が何か分りませんでしたが、半円形の部分がマイクロフォン(下半分)で下にのびる黒い棒のような部分はマイクロフォン・スタンドであることが分りました。下と左端はP123の写真よりもう少し広く写っています。夢中人さまのフィルハーモニア管弦楽団の50周年記念誌の写真と同じかもしれません。 *「A Voice to Remember」EMIレコード75周年記念レコード(1898-1973)。 英EMI EMSP75(2record set)付属の写真集P37より。
| |
