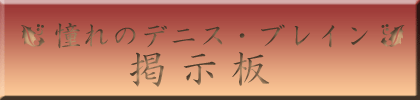
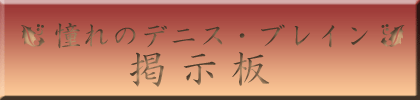
410.レイフ、イアン、ティモシーのフランツ作曲「流れの上で」 | |
| name: | 宮さん - 2003年02月19日 22時13分07秒 |
私にとってはCDがオリジナルであり、LPもしくはSP時代の話を聞いたり読んだりすると、悔しくなるばかりである。夢中人さんが指摘している「ノイズ除去やイフェクト過剰」な音質改善(いや改悪か)は、重要な問題であろう。 しかし、今日は「流れの上で」。というのも、「流れの上で」達人でいらっしゃる大トトロさんの掲示板を覗いたところ、私の愛聴盤が結構話題にのぼっていたからである。大トトロさんはその盤をご存じなかった。なぜなら、レイフ・オヴェ・アンスネス弾くフランツ・シューベルトのピアノ・ソナタ第20番の後に目立たないように収められている盤なので。テノールはイアン・ボストリッジ。私が“夢の中で”ブレインやリパッティと共演させている恐ろしく魅力的な歌い手である。ホルンはティモシー・ブラウンという人で、先の掲示板によると、この人はBBC響の主席で王立音楽院の教授ということだ。シヴィルの弟子とも書いてあった。このホルンはボストリッジの清らかな表現に比べると若干物足りない。このことについては、アンスネスも同様で、このCDの主人公は一体誰なんだと言いたくなってしまう。シューベルトの壊れてしまいそうな叙情をもっと繊細に表して欲しかった。とはいうものの、シューベルトの心の襞には触れていると思う。ボストリッジがあまりにも良すぎるのかもしれない。これは、是非とも皆様に聴いて欲しいCDである。この間東芝EMIの悪口を言っちゃったので、宣伝してあげます! | |
409.改善された?CDの音質 | |
| name: | 夢中人 - 2003年02月19日 0時14分01秒 |
私はLPレコードのコレクターではないので、うかつなことは言えませんが初期盤LPがあのように高価に売買されたり、Testamentが復刻LPを出しているということは、LPの音質がまだまだ捨て難い、あるいはCDはまだオリジナルLPに敵わないのではないか、と思ったりします。 私の場合、デニス・ブレインのモーツァルトやシュトラウスの再発売は原則(渋々)入手なのですが、LPとの出会いがあの忌わしき擬似ステレオだったため、トラウマとなってしまって現在でも東芝の擬似ステレオCD(TOCE-3042、P1995)には決して手が延びません。 CDも最近かなり改善されたようには感じますが、当初ダビングしたLPのゴーストが聞こえたり、ノイズ除去やイフェクト過剰でまるでサウンドに力が無かったり、バスが全然聞こえなかったりで、大抵満足出来ませんでした。 例外は同じく東芝EMIによるモーツァルト/コシ・ファン・トゥッテ(CE30-5464/66、P1989?)。パンチの効いた音で本家EMIのartシリーズ(CMS 5 67138 2、P1999)にも負けません。またブレインのモーツァルトの協奏曲では、作曲者の没後200年(1991年)に先駆けてモノラルで出たディスク(TOCE-6584、P1990)は音が良いと評判でした。 となんのかんの言いつつ、聴き比べながら音楽に浸ってしまうのは演奏が素晴らしいからでしょうね。 | |
408.ブレインのホルンはステレオよりもモノラルの方がよく聴こえる | |
| name: | 宮さん - 2003年02月18日 21時30分36秒 |
掲示板399では、クレツキのステレオ録音についての懇切丁寧な回答を、ありがとうございました。また、掲示板16の「ステレオ録音について」も大変参考になります。 ビーチャムの「幻想」に関しては、近所のCDのキャプションを見て、「へー、1年後に再録しちゃうんだね」と驚くと同時に、モノラルからステレオへの過渡期の混乱した状況を垣間見た思いがします。デッカではバックハウスの「ディアベリ変奏曲」も2種類あり(こちらは同録音ですが)ファンとしては結局両方買ってしまうことになります。経済的ではありませんね。 アナログからデジタル録音への移行期にも似たような現象が散見されますが、財布の紐が緩みつつも買ってよかったなあと思ったのが、グールドの「ゴルトベルク変奏曲」のアナログ・マスターから新しくマスタリングされた盤です。これは見違えるほど音がよかった! さらに、おしゃべりをつづけると、ビーチ・ボーイズの超名盤「ペット・サウンズ」(1966)のステレオ盤が1996年に初めて世に出たときは、感極まりました。モノラルでは聴こえなかった音までようく聴き取れるのですから。しかし、ここにはまた一つの大きな問題がありますので、詳述はさけます。 やっと、ブレインです。これは、私の単なる思い込みかもしれませんが、ブレインの音は、ステレオよりもモノラルの方がよく聴こえるのです。ステレオ初期の空間の捉え方がどうも未成熟で、ホルンの音が拡散されてしまうようなのです。一言で言えばブレインの魅力が半減してしまっているように感じられるのです。殊に交響曲の中のホルン独奏を聴くとその思いが強くなります。例としては、シルヴェストリとのチャイコフスキー第5番を挙げておきましょう。室内楽でのステレオ録音が聴けたのなら印象は変わるかもしれません。 逆に言えば、モノラルの固い音の方が、それがウン十年の後にマスタリングされたものであっても、ブレインの資質にあっているような気がするのです。この仮説は当然私自身の「印象仮説」ですので、多分に個人的な見解を述べたものにすぎません。掲示板の先輩諸氏とはいつも毛色の違う書き込みで悪いなあと思いつつも、ますますブレインが好きになっていくこの頃ですので、私の思いを記録に残すつもりで、キーを叩きました。 追記:BLUE NOTEがブレインを録ったら最高の響きになったでしょう。 | |
407.ミュンシュ/ソシエテ/ロンドン録音(400) | |
| name: | Favart - 2003年02月17日 22時32分05秒 |
この録音はまだ聴いていませんが、ホルンはテヴェ、フルートはラヴァイヨでしょうか。1946年6月ロンドンで、やはり1930年代にソシエテで活躍した大指揮者ピエロ・コッポラがナショナル交響楽団(DB在任中)とシューマンの第1交響曲を録音しています。DANTEのCDでは録音場所は定かでありません。 トルトゥリエがビーチャムに認められシュトラウスの「ドン・キホーテ」を演奏した経緯はトルトゥリエの自伝に書かれていたと思います。トルトゥリエの弟子の倉田澄子さんの日本の家に泊まり、日本式風呂に入るのが気にっていたといったことが書いてあったような気がします。1972年頃来日した時の話でしょうか。(間違っていたら失礼)
| |
406.「牧場の朝」とブレインのおかげで今の私がある | |
| name: | 宮さん - 2003年02月16日 23時07分27秒 |
うーん、先輩方にまるっきりついて行けない。しいて言えば「牧場の朝」か。これは、私が唯一ピアノ弾き語りができた曲。教員採用試験のために無我夢中で練習したのだった。(職業がバレちゃったか?)。現在では4年生の教科書に載っている。 思えば、採用試験の朝にブレイン/カラヤンのモーツァルト:ホルン協奏曲第1番を景気づけに聴き、本番では「牧場の朝」をオルガンを弾きながら歌ったのであった。結果は見事合格。そして今がある。ありがとう、「牧場の朝」そして、ブレイン。 (またまた、予告。近日中に「教科書から消えたモーツァルトのホルン協奏曲」という題名で書き込みをさせてください。新指導要領になり、この名曲が鑑賞教材から抜けてしまったという話。) | |
405.弦と管 | |
| name: | CATO - 2003年02月16日 23時05分06秒 |
「クラシック音楽といえばピアノとヴァイオリンで、管楽器はガクタイ(楽隊)のすること」。このイメージやはり根強いですね。私の経験でも、学生オケで、令嬢・令息はずっとやってきたバイオリンなどを引き続きやり、管はブラスバンド経験のあるサラリーマンの子弟がやる。これがパターンでした。あるN響メンバーの座談会で、この状況を面白おかしく述べているのを見て、大笑いした経験があります。 これは単なるいきさつにしか過ぎないのに、偏見に流れることが確かにありますね。欧米での弦管棲み分け状況はどうなんでしょうか。 | |
404.邦人による第九初演と海軍軍楽隊 | |
| name: | 夢中人 - 2003年02月16日 11時16分24秒 |
Favart様、木下様、CATO様のお話、特別な思いを持って読みました。ありがとうございました。 昨日、神戸新聞編集委員、山崎整さんによる講演会《船橋栄吉の「牧場の朝」》に参加しました。そのお話の中で1924(大正13)年11月29日、東京音楽学校奏楽堂におけるベートーヴェン/第九交響曲の邦人初演は、弦楽器は音楽学校の教師、学生、OBが、管・打楽器は海軍軍楽隊々員を中心とした応援メンバー、と当時の音楽家の総力を結集したものだったことを伺いました。 人生の大先輩方が今でもクラシック音楽といえばピアノとヴァイオリンで、管楽器はガクタイ(楽隊)のすること、というイメージを持っているのはそんな時代背景があったからと想像します。 講演会の最後は、オリジナル譜による再現演奏へのアンコールと聴講者によるちょっと控え目な「牧場の朝」の合唱で閉じられました。 西洋音楽黎明期に活躍した万能音楽家、船橋栄吉の足跡についてはこちらをご覧下さい。 | |
403.團と芥川 | |
| name: | CATO - 2003年02月16日 6時21分10秒 |
Favartさんの文章をきっかけに少々私も。 團伊玖磨:それこそ40年近くも前と思いますが、團が読売日響を相手にトークと演奏を行なう番組がありました。名曲になじむことを指導してくれた懐かしい番組です。思い出すのは、ピアニストの清水和音がほんの小さいときに(3,4歳?)マスコットボーイ的に出ていたことです。かなり前ですね。「和音とは、将来音楽家になるような名前やなあ」と思っていたら、本当になってしまいました。團伊玖磨の曲といえば、私には「花の町」と「祝典行進曲」です。「祝典行進曲」はブラスバンドのとき、トランペット又はアルトホルンで何回も演奏しましたが、華々しく、各楽器の見せ場が充分に考慮されており、しっとり来る旋律が素晴らしかったです。名作とされる「夕鶴」は、私にとっては心に残る歌と旋律がなく、馴染めませんでした。 芥川也寸志:といえば、野際陽子とのコンビの、サントリー「百万人の音楽」です。これまた昔でして、30〜40年前だったでしょう。大阪での公開演奏会にも行きました。モーツァルトの40番がメインであった日です。 この番組もクラシックオタク予備軍の中高生に大きな影響を与えたと思います。芥川のコメントで今も覚えている例として「ホルンはチェコフィルがいい」「ウィーンフィルのトランペットで、フェルムートというのがいて、これが名人で」なんかがあります。シラミの歌の紹介もありました。残念ながら、芥川の作品はほんの少ししか知りません。「忠臣蔵」のテーマが有名すぎました。なお、岩波新書の「音楽の基礎」は出た時に買って、今も読み返す本です。 二人とも、今後まともに作品を聴いてみたいものです。 | |
402.陸軍軍楽隊とギャルド | |
| name: | 木下直人 - 2003年02月16日 6時01分34秒 |
参考までに・・陸軍軍楽隊の大沼哲楽長と、同じく陸軍軍楽隊出身で戦後警視庁の音楽隊長になられた山口常光氏は戦前にギャルドに留学されています。初代陸上自衛隊中央音楽隊長だった須摩洋朔氏も、陸軍軍楽隊の出身で大沼哲楽長から学んでいます。この伝統は現在でも守られているようです。ちなみに、海軍軍楽隊の伝統は、戦後消防庁音楽隊の内藤清伍氏(海軍軍楽隊長)によって引き継がれました。音楽の友社社長だった堀内敬三氏は1914年に留学先のアメリカで、たまたまアメリカ演奏旅行中だったギャルドの演奏を聴き、その素晴らしさに驚嘆されたそうです。これらの人たちによって管楽器によるフランス音楽がわが国に紹介されたのです。 | |
401.エスカルゴの歌 | |
| name: | Favart - 2003年02月15日 23時46分46秒 |
|
今は亡き團伊玖磨さんの名随筆「エスカルゴの歌」の中に「鼓手の思い出」という題の随筆があり、陸軍戸山学校軍楽隊のことが書かれています。[「すみれ新書」(昭和40年)。後に朝日文庫で復刻されました。] 「昭和19年の10月1日は小雨のそぼ降る薄ら寒い日だった。僕は、暗い心にともすれば渋る足を曳き摺るようにしながら、省線新大久保の階段を降りて行った。今日から陸軍戸山学校軍楽隊の一員として兵役に就くためである。・・・」との書き出しで、陸軍戸山学校の思い出が書かれています。 「陸軍軍楽隊は、正式には陸軍戸山学校軍楽隊と言うのが正しく、・・・」とのことで入学(隊?)試験があり、團氏の他に上野の音楽学校から14人が試験を受けて全員が合格したとのことです。その中には作曲家の芥川也寸志氏もおられ、入隊後の楽器の割り当ての様子がおもしろく書かれています。 ・・・試験官は、僕の隣に並んでいた芥川に言った。「お前の顔は長いな。テノール・サクソフォン!」僕に言った。「お前は痩せていて肺病になるといかん。小太鼓!」・・・といった調子で、あてずっぽうに割り付けられた楽器を練習したとのこと。 また、「最も馬鹿らしかったのは、陸軍はフランス系統の伝統を持っていたので、楽器の名前や音名はすべてフランス語を使わないと叱られることだった。うっかり「小太鼓」などと言おうものなら、なぜプチ・ケースと言わんか!小太鼓などと民間人のようなことを言うな!と殴られる。オーボエはオーボア、ファゴットはバッソンと言わなければ大事になるのだった。・・・その頃フランスは敵性国家であり、フランス語はむしろ言えば工合の悪い状態だったのだが・・・。・・・ (こうしてみると、陸軍戸山学校軍楽隊はギャルドとつながりがあったのかもしれません。) また、この随筆ではありませんが、團氏と、芥川氏が陸軍戸山学校軍楽隊時代に作曲した「シラミの歌」というのがあり、おもしろいのでご紹介します。たぶん、「パイプのけむり」に書いてあったと思います。 「ソラソラシラミー、ドラドラシラミー、ミレドミレドシラミー、シラミー」 といった他愛のないものですが。 「エスカルゴの歌」は「湘南博物誌」、「五線のうちそと」の二つの部分からなり、音楽以外の話がほとんどですが、私の好きな随筆です。 | |
