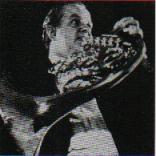Y 忘れざるルシアン・テーヴェ Z
掲示板(221-230)
戻る 次へ
230.ヌオーについて
投稿者:koba - 2001年12月22日 17時52分13秒
大山様。
ミシェル・ヌオーにつきましては、私もそれほど多くのことを知っているわけではありませんが、ざっと経歴を説明すると以下の通りです。
生まれは1924年で、1943年には第二期生としてマルセル・ミュールが教授を務めるパリ音楽院に入学。
ちなみに前年の1942年にパリ音楽院サクソフォン科が再開された時の第一期生はダニエル・デファイエとジャック・テリー。
(日本ではジャック・テリーといえばデファイエ四重奏団のテナー奏者として知られていますが、長らくギャルドのテナー主席を務めた、つまりミシェル・ヌオーの同僚でもあった人です)
参考までに日本でもある程度、名の知られた主な人たちの入学年度は以下の通りです。
1942年 ダニエル・デファイエ、ジャック・テリー(デファイエ四重奏団のテナー奏者)
1943年 ミシェル・ヌオー
1947年 ジャン・ルデュー(デファイエ四重奏団のバリトン奏者)
1948年 アンリ・ルネ・ポラン(デファイエ四重奏団のアルト奏者)
1951年 ジャン・マリー・ロンデックス
1958年 アンドレ・ブーン(ミシェル・ヌオーの後任としてギャルドのアルト主席を務める)
1952年には初のジュネーヴ国際音楽コンクール・サクソフォン部門で第1位を獲得、長らくギャルドのアルト主席(最高楽手)を務めた後、1979年に定年によりギャルドを退団。
ギャルド在団中は、1928年にマルセル・ミュールによって結成された伝統あるパリ・ギャルド四重奏団のリーダーとしても活躍し、ショルティーノの「異教徒の踊り」(1960年)をはじめとして、多くの作曲家から曲を献呈されています。
また、ソシエテの時代から演奏会、録音に多く参加し、パリ管の時代にはソリストを務めました。
ここは多少説明が必要かもしれませんが、ソシエテ時代には当初マルセル・ミュールが呼ばれており、その代役としてダニエル・デファイエやミシェル・ヌオーが呼ばれることもあったようですが、彼が録音からも引退した1960年代に入るともっぱらダニエル・デファイエかミシェル・ヌオーが呼ばれ、1968年にパリ管に改組されてからは正式にソリストとしてクレジットされたようです。
残念ながら録音は少なく、ピアノ伴奏等によるソロは1曲だけ存在するという話ですが未確認です。(市販はされなかったようです)
オーケストラでの録音は、クレジットされているものとしては、クリュイタンス指揮「アルルの女」、ボド指揮「展覧会の絵」、バレンボイム指揮「アルルの女」等、またギャルドの録音でも多くのソロを聞くことができます。
ギャルドの録音については、何時アルト主席に就任したか不明ですが、少なくともロジェ・ブトリーが指揮者に就任した時には既にアルト主席だったので、1970年代の録音はすべて彼のソロということになります。
またアンサンブルとしての録音は、パリ・ギャルド四重奏団の2枚やパリ・リード楽器アンサンブルの2枚(共に仏AFA)等があり、特に後者では彼の濃厚なソロを聞くことができます。
演奏そのものについて言葉で説明するのは難しいのですが、スタイル的にはマルセル・ミュールをそのまま受け継いだといってもよく、言い換えれば現代からすると(クロード・ドゥラングル等は勿論のこと、ジャン・マリー・ロンデックスあたりと比較しても)「古いスタイル」と言えるかもしれません。
また「音」そのものに関しては、ダニエル・デファイエやジャン・マリー・ロンデックス等に比べれば、はるかに「ミュール的」な甘美な美音と言えますが、やはり音の濃さ(特に中音の倍音の含まれ具合)という点でミュールとはかなり異なります。
ダニエル・デファイエはマルセル・ミュールから受け継いだ「音楽」をそのまま手付かずで生徒に受け渡したようですが、「音」そのものはマルセル・ミュールとは全く別物の「デファイエ的」とも言える独特のものがあり、それを受け継ぐ人もいないと思われます。
あえて言えば、須川展也が世間的には「まるでミュールのような音」と言われたりしていますが(笑)、むしろ「デファイエ的」な音に近似性があるような気がします。
(ちなみに私は、プロデューサーの磯田健一郎にまるで食い物にされているかのような、ここ数年の須川展也とトルヴェールの演奏には興味を失っています)
そもそも「ミュール的」な音は時代遅れと捉えられ、現代の若手は誰もそれを追ってはいないのではないでしょうか?
その意味で、日本のサックス奏者に影響が大きかったのはジャン・マリー・ロンデックスだったのではないかと思います。
ある意味、パワフルでストレートな彼の音は、現代曲にも向いたもので、時代的にも迎合されやすかったのかもしれません。
ロンデックス門下は勿論のこと、デファイエ門下の武藤賢一郎(M氏?)にしても、音的にはジャン・マリー・ロンデックスに近いものを感じます。
それとミシェル・ヌオーの演奏に関してもう1つ言えることは、音楽的には1980年代まで素晴らしい演奏を聞かせてくれましたが、「音」そのものの魅力ということで言えば、彼の絶頂期は1960年代までで、1970代以降はいわゆる「艶」がなくなり、残念ながら昔の面影はありませんでした。
尚、ミュールのダマーズですが、1950年代後半に現役を一応引退し、1960年代前半には録音も含め演奏家としては完全に引退してしまった(パリ音楽院の教授を退任したのは1968年)ことを考えると、可能性としては1950年のコンチェルトシュトゥックあたりになると思いますが、私の記憶にはありません。
LP時代のマルセル・ミュールの録音といえば、イベール等の有名どころにセルマー(セルメアというべきかも)のデモンストレーション用の数枚、エラートにいれた唯一?のステレオ録音等が知られていますが、確かダマーズはなかったはずです。
(時間がとれた時にじっくりと確認はしてみますが)
最近はビデオが発売されたりもしていますので、今後発掘される可能性に期待したいところですが・・・。
229.ヌオーという人について教えて下さい
投稿者:大山幸彦 - 2001年12月21日 14時05分54秒
koba様。私素人で恐縮ですが、高名なD氏はよく言われているのはぜんぜんちがってミュールとは音はあまり似ていない、と思うのですが、ヌオーという方はどうなのでしょう?私のいとこ(工藤重典)の友人でこれまた高名なM氏という方がいてD氏のお弟子さん、という事ですが、そのM氏の音もミュール系列とは思えないのですが。
私、一番すきな作曲家はフランセ、ボノ、ダマーズ、デュボア、ボザ、プーランク、イベールあたりですが、ミュールのダマーズなんかありませんかねえ。vacanseもかなわぬこととはいえ、ミュールの音で聞いてみたかった(kobaさん音源はありませんか?)
228.カラヤン
投稿者:大山幸彦 - 2001年12月19日 15時34分55秒
の本でパリ管監督就任については1ページしかふれられていませんが、大変興味のある事が書いています。ドゴールが承認し、ポンピドウが解任しショルティを採用したとの事。キャリアの最後は親独になったドゴールと、最後はドゴールと仲たがいし独自の東欧政策をとろうとしたポンピドウ。音楽はまるで政治の道具ですが、そんな私は今1914−24のポアンカレ=クレマンソー時代に少し興味があります。この時代に我々をとりこにしてやまぬ様々な芽がありそうです。
227.追記
投稿者:koba - 2001年12月16日 17時56分57秒
久しぶりにギャルドのHPをのぞいたら、団員の募集をしていました。
ちなみに楽器はクラリネットとユーフォニアム。
募集要領を見ると、フランス国籍であること、18〜36歳までの年齢制限の他、身長が男性は170cm以上、女性は160cm以上となっていました。
身長にも制限があるのは昔、誰かのインタビューか何かで読んだ記憶があるのですが、女性が160cm以上というのにはちょっとビックリ!
日本だったら身長制限で涙をのむ人が多いかもしれませんね。
でもクラリネットの女性団員のシルヴィー・ユーはどう見ても160cm以下だと思うのですが・・・。
随分前の来日時に、遂に女性団員が入団したということで、思わずサインを頂きましたが、その時の印象は本当に小さく可愛いお嬢さん!といった感じでした。
身長制限も時代によって変化するのでしょうか?
ちなみにその時、打楽器にも女性がいましたが、その方は大変大柄(縦も横も)でしたね(笑)。
226.当掲示板との出会い
投稿者:koba - 2001年12月16日 16時23分36秒
大変ご無沙汰しております。
最近は忙しい合間をぬって、皆さんの書き込みを拝見するのが楽しみの一つになっています(笑)。
当掲示板はテヴェをはじめとして、クリュイタンス、ソシエテ、ギャルド等、私の愛する音楽家達の話題に溢れ、他では味わえない至福のひと時を約束してくれます。
そもそも私の音楽との出会いが、小学5年の時に初めてサックスを手にし、たまたま参考に購入したレコードがクリュイタンス指揮ソシエテの「アルルの女」組曲でした。
そこでサックスを吹いていたのがギャルドのソリストを長年務めたミシェル・ヌオーだったことから、クリュイタンス、ソシエテ、ギャルドといったものに対する音楽的嗜好が決定的になったようです。
その後、遺産という形で1万枚程のレコードを譲り受け、また高校生の頃からオークションやらセットセールやらで海外からせっせとレコードを購入していたもので、今では自分でも何が何処にあるかも分からないような状態ですが、そんな中で、すぐに聞けるよう手元の棚に格納されているレコードの多くはクリュイタンス、ソシエテ、ギャルドといったところを中心に、所謂フレンチスクールの演奏家のものが大半です。
そんな私からすると、テヴェを中心にコルに関するこれだけ多くのお話を拝見できるのは正に天国であり、ギャルド研究家(とお呼びすれば良いのかしら?)の木下直人さんのお話にはいつも興奮させられます。もしかするとギャルドのディスコグラフィーなんてものもご自分で作成しておられるのではないかと、密かに期待していたりします(笑)。70年代以降のギャルドに対してどのような意見をお持ちかも興味あるところです。
とりとめもなく書いてしまいましたが、当掲示板との出会いはネットに関連した事柄では今年一番の収穫であり、今後もいろいろな話題で楽しませて頂きたいと思います。
225.ヴィタリー・ブヤノフスキーのこと
投稿者:夢中人 - 2001年12月16日 16時04分45秒
年末につき棚を整理していますと、亡くなったケルに送る筈だったレニングラード・フィルハーモニー交響楽団の東京ライヴのCDを見つけました。
亡くなる前のケルは日本でのみ発売されるホルンのレコードに大変興味を示しており「このCDも是非欲しい。彼(ブヤノフスキー)のロッシーニのプレリュード・・そしてシューマンのアダージョ・・偉大なホルン演奏のひとつ」と言ってきたのが最後となりました。
私はその1973年来日公演を、期待を持って聴いた何千もの日本人の一人ですので、大変懐かしく早速開けてみました。ブックレットでムラヴィンスキー夫人があの時の首席フルートだったことを知り、先日新聞でムラヴィンスキーの自作譜が発見されて、その中にタンゴが混じっていたことを夫人が語った記事と、NHKテレビで見た彼の峻厳な顔とのギャップが大変面白く感じられました。
あの日、仕事で遅くなってしまって演奏会場の大阪フェスティバルホールにたどり着いた時には既に舞台に着席し終わっていて、プログラムはベートーヴェンの4番とショスタコーヴィチの5番の二曲。名前は失念しましたがテレビで見た東京公演では襟に赤い国家功労芸術家の勲章をつけて物凄いベルアップで仲間内で話題をさらっていた首席Tptは「歯が欠けた」という噂で出ていませんでしたが、
オールバックで一見ゴッドファーザーの時のマーロン・ブランドのような風貌のヴィタリー・ブヤノフスキーは、確実なイントネーション、抑制の利いたヴィブラート、全く危なげないソロで私を唸らせました。
アンコールの「ルスランとリュドミーラ」がまた凄い演奏で、皆(吹奏楽団なのに)今度のコンクールでやろう!って言ったのを覚えています。
ブヤノフスキーのレコードにはケルのお気に入りのシューマンやロッシーニ、テレマンの協奏曲(ウラジミール・シャリト、アンドレイ・グルホフ、ワレンチン・バイコフらと)のほかに、リヒャルト・シュトラウスの第1協奏曲があるのをご存知でしょうか(BMGビクター、BVCX4006)。1964年4月24日、レニングラード・フィルハーモニー大ホールでのライヴ録音と言いますから、丁度日本にパリ音楽院管弦楽団が来日して聴衆の度肝を抜いたのと同時期の演奏ということになります。
ヴィタリー・ブヤノフスキー(1928-1993)。レニングラード生れ。父でありレニングラード国立音楽院教授にしてレニングラード流派の創始者、ミカエル・ブヤノフスキー
(1891-1966)にホルンを学び、戦後1946年から1956年までキーロフ歌劇・バレエ交響楽団、1953年プラハ国際コンクール優勝、1955年、レニングラード・フィルハーモニー交響楽団入団、1959年ウィーン国際コンクール優勝、1988年ムラヴィンスキーの死去とともに退団後も北欧、東欧をはじめアメリカ、カナダでも多くを教えた。世界が東西南北で境界されていた時代に活躍した偉大なるホルン奏者の一人でした。
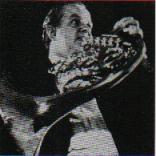
ヴィタリー・ブヤノフスキー
224.個を考える
投稿者:夢中人 - 2001年12月15日 22時24分43秒
今年は21世紀の最初ということもあり、大山さんやKAZUさんとの出会いから始まったルシアン・テヴェのページ、未だ完成を見ないながらデニス・ブレイン生誕80周年CD制作といった二大イヴェントを手掛けた上、公私にわたり未曾有の混沌とした状況に陥りましたので一生忘れ得ぬ年となることは間違いありません。
そんな年も師走となりましたので恒例のベートーヴェンの第9を聴きました。いつもならフィルハーモニア/フルトヴェングラー(ルツェルンの第9)を選ぶのですが、今年はパリ音楽院管弦楽団/カール・シューリヒト(EMI
CZS 7 62910 2)とコンセール・ラムルー管弦楽団/イーゴル・マルケヴィチ(Philips
PHCP-20411)の登場です。
どちらもスレンダーな弦楽器と管楽器の響きが心地良く、コルのヴィブラートも適所でセンス良く聞こえて素晴らしいです。実は高校生の頃より、第9といえばバイロイト祝祭管弦楽団/ウィルヘルム・フルトヴェングラーが決定盤、という呪縛に長らくとらわれていましたが、三十位の頃、上記ルツェルンの第9を聴いてからというものの、音楽を指揮者で聴くのではなくて演奏者で聴く、という聴き方が身に付きました。
つまりルツェルンの第9は、フルトヴェングラーの棒のマジックもさることながら、デニス・ブレインの特大の音やティンパニ(ジェームズ・ブラッドショウ)の気合、美しいバスーン(セシル・ジェームズ)、火花を吹くようなトランペット(ハロルド・ジャクソン)等などあちこちで繰り広げられるフィルハーモニアの奏者の名人芸が心を捉えて止まないのです。
全体よりも個に向かう興味はもう止め様がありません。そんな訳で今年Orfeoから新発掘として出されたフルトヴェングラーの何番目かの第9(ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団)には触手が伸びませんでした。全体的にもあまり話題にならなかったのは以前なら考えられない事です。ひとつにはリチャード・オズボーンの著書「ヘルベルト・フォン・カラヤン」にあるように神格化されていた巨匠が実はとても人間くさい人柄であったことが暴露されたことも絶対的人気を凋落させた原因になったのかも。
一方レコード音楽は既に100年近い歴史があり、録音技術も飛躍的に向上して年々増え続けてきたカタログが今にきて急にブレーキがかかったのはどういう訳でしょうか。私は現代の演奏がいくら上手だったとしても、世界中どこに行っても同じような音色だったとしたら聴きたいとは思わないし、懐古趣味と言われても古い演奏でも良いものは良い、と大きな声で言いたいのです。そんな意味で今まで行われてきたあらゆる統一化の流れは、個人的には懐疑的です。
そんな今年、ギャルド・レピュブリケーヌ軍楽隊の研究家、木下直人さんとの出会いは私にとって貴重な、大切なものとなりました。ギャルドを中心にしたフレンチ・スタイルの音楽とその再生に関する情熱とご経験・知識は誰よりも深いものをお持ちなのに、私のような無知なる新参者を同好の士として扱って下さったのには本当に驚きと感謝の念に絶えません。
レコードとして吹奏楽を、あるいは歴史的録音をきちんとした形で残したのが木下さんのような個人の力であること自体、現代のクラシック音楽にとって象徴的なことのように考えています。また注目しているのは出版におけるオン・デマンドのような形態です。いつでも好きなものが手に入らないものかと。
ちょっと支離滅裂となりました。お詫びして終わります。
223.アンドレ・クリュイタンス、フランス音楽を振る
投稿者:夢中人 - 2001年12月15日 9時34分17秒
TestamentのHPで近日発売とされています。ともかくその数の夥しさに驚きです。
●ベルリオーズ
幻想交響曲作品14
フランス国立放送局管弦楽団
ロミオとジュリエット作品17 抜粋
パリ国立歌劇場管弦楽団
SBT
1234
●ビゼー
「アルルの女」第1、第2組曲
序曲「祖国」作品19
交響曲ハ長調
フランス国立放送局管弦楽団
SBT 1235
●ドビュッシー
玩具の箱
子供の部屋
ラヴェル
クープランの墓
高雅にして感傷的なワルツ
フランス国立放送局管弦楽団
SBT
1236
●フランク
交響的変奏曲
●ダンディー
フランス山人の歌による交響曲
アルド・チコリーニ
パリ音楽院管弦楽団
●フランク
交響曲ニ短調
フランス国立放送局管弦楽団
SBT
1237
●ビゼー
「美しいパースの娘」組曲
●ラヴェル
道化師の朝の歌
ダフニスとクロエ第1、第2組曲
古風なメヌエット
海に浮かぶ小船
フランス国立放送局管弦楽団
●ルーセル
蜘蛛の饗宴
パリ音楽院管弦楽団
SBT
1238
●ルーセル
交響曲第3番ト短調作品42
「バッカスとアリアーヌ」組曲第3番作品43
弦楽のための小交響曲作品52
交響曲第4番イ長調作品53
パリ音楽院管弦楽団
SBT 1239
●サン・サーンス
交響曲第3番ハ短調作品78
アンリエット・ロジェー
パリ音楽院管弦楽団
●フォーレ
レクイエム作品48
モーリス・デュリュフレ、マルタ・アンゲリチ、ルイ・ヌグエラ
サン・トゥシュタッシュ合唱団・管弦楽団
SBT 1240
このほかDutton Laboratoriesのスーパーバジェットシリーズ CDBP
9712
エルネスト・アンセルメ/リムスキー・コルサコフ「シェヘラザード」、ダッタン人の踊りほか
9700
エルネスト・アンセルメ/ストラヴインスキー/ペトリューシカ、火の鳥ほか
も大注目。ソシエテの「シェヘラザード」は木下さんのお宅でLPを聴かせて頂きましたがテヴェの夢のようなソロを堪能出来ます!
222.さらに
投稿者:大山幸彦 - 2001年12月05日 21時38分55秒
孫弟子さんのとこでもないです。
この稿、とりあえず失礼。
221.もちろん
投稿者:大山幸彦 - 2001年12月05日 21時32分21秒
ここやsonoreさんとこではないですが。むしろPC上じゃないとこで。
戻る 次へ