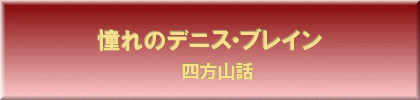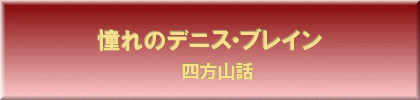| 第60話「フランダース&スワン/イル・ウィンド」 |
モーツァルトのホルン協奏曲第4番終楽章に声楽版「イル・ウィンド」というのがあります。パフォーマーは、1950〜60年代、大変人気を博したエンタテイナー、マイケル・フランダース(1923-1975)とドナルド・スワン(1922-1994)で、英国のある世代は、デニス・ブレインとハレ管弦楽団によるレコードのロンド楽章を聴くと必ず「フランダース&スワン」を連想するといいます。
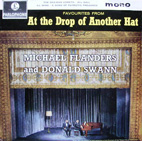 「イル・ウィンド」は、1963年、シアター・ロイヤルで行われたショー「アット・ザ・ドロップ・オブ・アナザー・ハット」のうちの1曲で、最近フレンチ・ホルンを練習しているというマイケル・フランダースが、モーツァルトが18ヶ月ぐらいのときに作曲したホルン協奏曲変ホ長調K.約495終楽章(??)を初演したい、という口上で始まったらしい。 「イル・ウィンド」は、1963年、シアター・ロイヤルで行われたショー「アット・ザ・ドロップ・オブ・アナザー・ハット」のうちの1曲で、最近フレンチ・ホルンを練習しているというマイケル・フランダースが、モーツァルトが18ヶ月ぐらいのときに作曲したホルン協奏曲変ホ長調K.約495終楽章(??)を初演したい、という口上で始まったらしい。
ドナルド・スワンは作曲家で、1956年ホフナング音楽祭のためのハイドンの交響曲第94番(びっくりシンフォニー)の編曲でも有名です。
|
2004年11月13日 12時59分06秒
| |